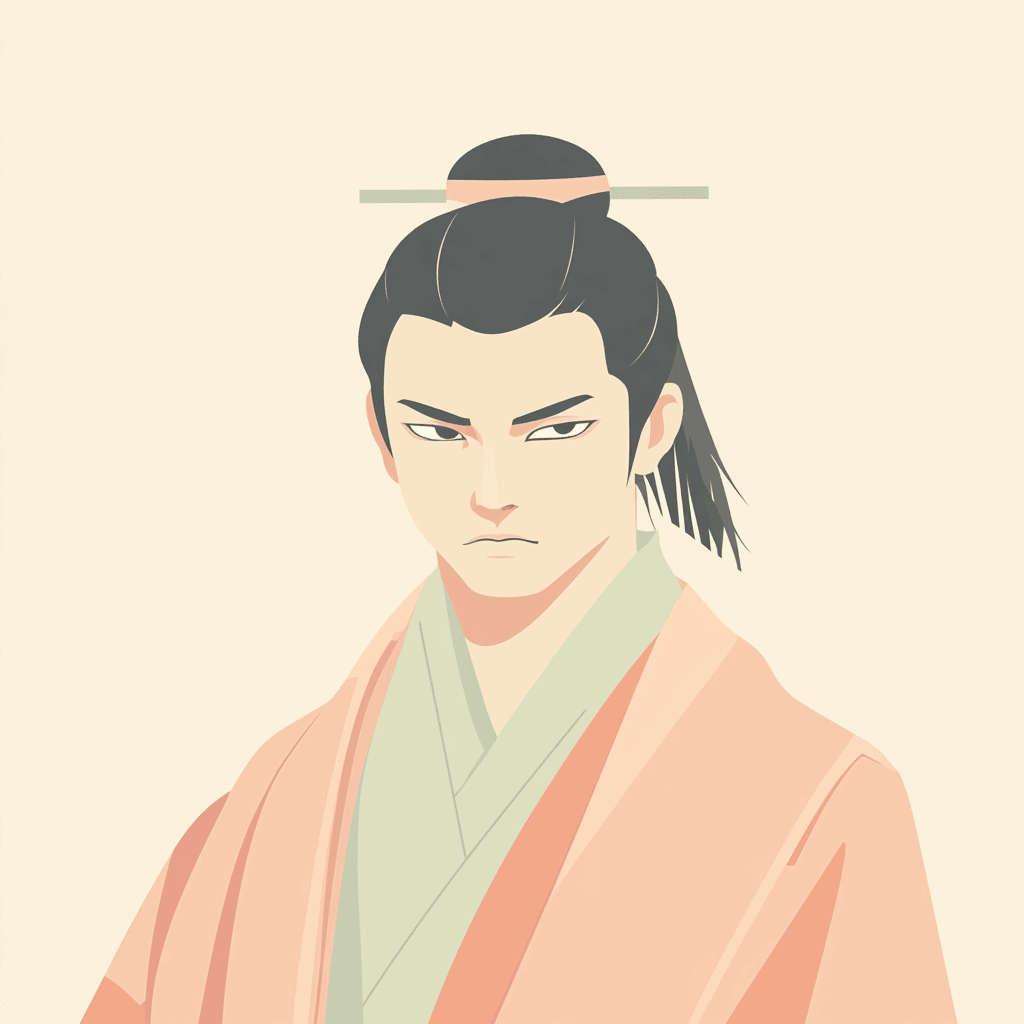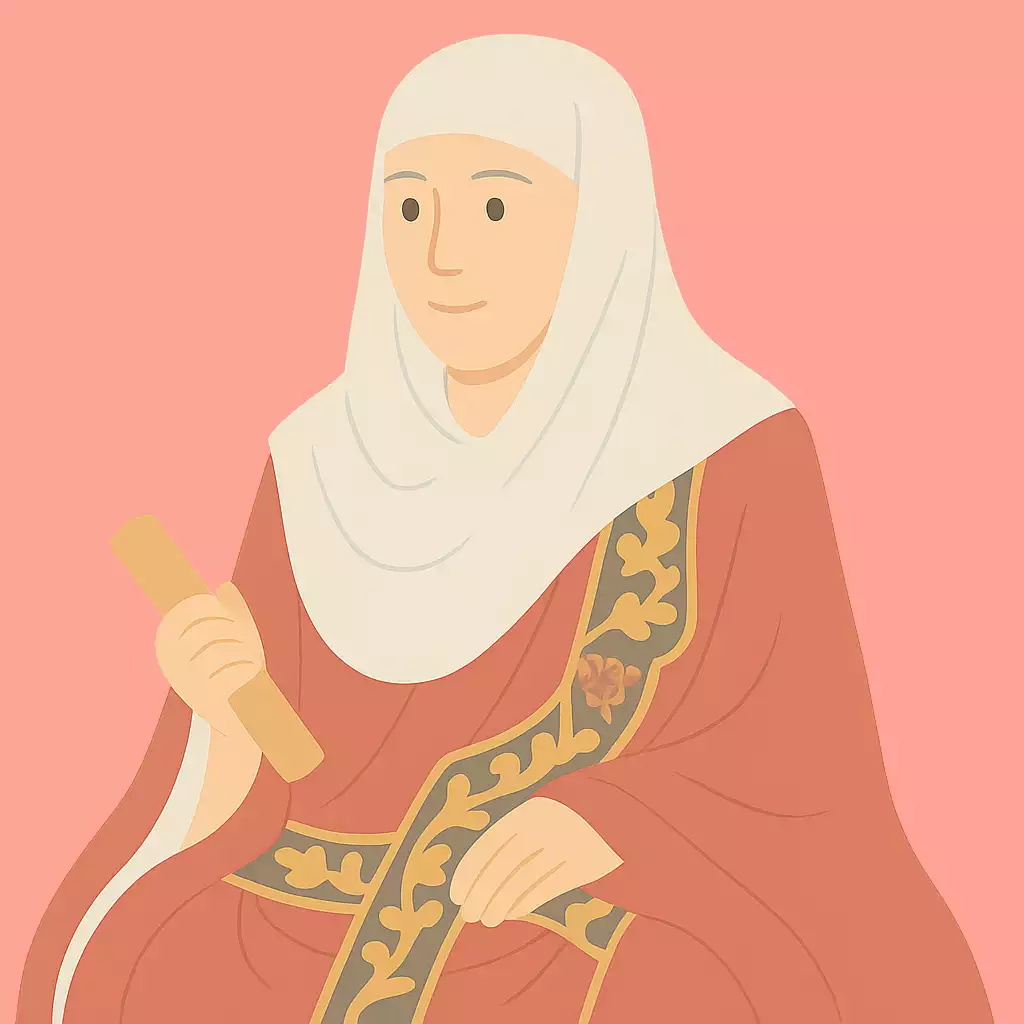第1章 幼少期の思い出
私の名前は内村鑑三。1861年、江戸時代の終わりが近づいていた頃、私は現在の群馬県高崎市に生まれました。父は武士で、私も武士の家に育ちました。当時の日本は、長い鎖国政策の終わりを迎え、急速な変化の時代に突入しようとしていました。
幼い頃から、私の心には大きな疑問が渦巻いていました。
「なぜ人は生きるのだろう?」
「この世界には、どんな意味があるのだろう?」
そんな疑問を抱えながら、私は日々を過ごしていました。父は厳格な人でしたが、母は優しく、私の好奇心を大切にしてくれました。
「鑑三、疑問を持つことは良いことだよ。でも、答えを見つけるのは簡単ではないかもしれないね」
母のその言葉は、私の心に深く刻まれました。
ある日、私は庭で遊んでいると、一匹の蝶が目の前を舞っていきました。その美しい姿に見とれていると、突然強い風が吹き、蝶は地面に落ちてしまいました。私はすぐに駆け寄り、そっと手のひらに乗せました。
「大丈夫かな?」と心配しながら見ていると、しばらくして蝶はゆっくりと羽を動かし始め、やがて再び空へと飛び立っていきました。
その瞬間、私の心に強い感動が走りました。「生きるってすごいな。どんなに小さな命でも、懸命に生きようとしている」
この体験は、後の私の人生観に大きな影響を与えることになりました。生命の尊さ、自然の神秘、そして諦めない心。これらの大切さを、幼い私は蝶から教わったのです。
夜、私はこの出来事を父に話しました。普段は厳しい父でしたが、その時は珍しく優しい表情を浮かべて聞いてくれました。
「鑑三、お前は良いものを見たな。命を大切にする心は、武士にとっても最も大切なものだ」
父のその言葉に、私は大きな喜びを感じました。同時に、「命」というものについて、もっと深く考えてみたいという思いが芽生えたのです。
第2章 学びの日々
時は流れ、明治時代になりました。1868年、明治維新により日本は大きく変わり始めました。私も15歳で上京し、英語を学び始めました。当時の日本は、欧米の文化や科学技術を急速に取り入れようとしていた時代。私も、その新しい知識の波に飲み込まれていきました。
英語の授業は、私にとって新しい世界への扉を開くものでした。最初は難しく感じましたが、日々の努力で少しずつ上達していきました。
ある日の授業で、先生が聖書の一節を英語で読み上げました。
“God is love.”
「神は愛なり」
その言葉に、私は心を打たれました。それまで知っていた神々とは全く違う、愛に満ちた神の存在。それは、私の心に大きな衝撃を与えました。
授業後、私は先生に尋ねました。
「先生、この『神は愛なり』という言葉、どういう意味なのでしょうか?」
先生は優しく微笑んで答えてくれました。
「内村君、それはキリスト教の中心的な教えの一つだよ。神は全ての人を無条件に愛している、ということなんだ」
その説明を聞いて、私の中にさらに多くの疑問が湧いてきました。
「でも先生、もし神が全ての人を愛しているなら、なぜこの世界には苦しみがあるのでしょうか?」
先生は少し考え込んでから答えました。
「それは難しい質問だね、内村君。多くの哲学者や神学者が何世紀もかけて考えてきた問題だ。簡単な答えはないけれど、考え続けることが大切なんだよ」
この会話は、私の心に深く刻まれました。同時に、キリスト教についてもっと知りたいという思いが強くなりました。
しかし、同時に疑問も湧いてきました。「本当にそんな神が存在するのだろうか?」「日本の伝統的な信仰とどう折り合いをつければいいのだろうか?」
その疑問を胸に、私はさらに学びを深めていきました。英語だけでなく、歴史、哲学、科学など、様々な分野の知識を貪るように吸収していきました。
この時期、私は幼なじみの太郎とよく議論をしました。太郎は伝統的な価値観を大切にする家庭で育ち、西洋の思想に懐疑的でした。
「鑑三、お前は西洋かぶれになってしまったんじゃないのか?」と太郎は言いました。
「違うんだ、太郎」と私は答えました。「僕は日本の伝統も大切にしている。でも、新しい考え方を学ぶことで、もっと広い視野を持てると思うんだ」
太郎は納得していないようでしたが、「お前の言うことはよく分からないが、お前なりの道を進んでいけばいいさ」と言ってくれました。
この会話は、後の私の思想形成に大きな影響を与えることになりました。伝統と革新、東洋と西洋、これらを調和させることが、私の生涯のテーマの一つとなったのです。
第3章 札幌農学校での日々
18歳になった私は、北海道の札幌農学校(現在の北海道大学)に入学しました。北海道は、当時まだ開拓が進められている新天地。そこで学ぶことは、新しい日本を作り上げていく一員になるような感覚でした。
そこで出会ったのが、アメリカ人教師のウィリアム・クラーク博士でした。クラーク博士は、私たちに農学だけでなく、人生の哲学も教えてくれました。
入学して間もない頃、クラーク博士は私たち学生に向かってこう言いました。
「Boys, be ambitious!(少年よ、大志を抱け!)」
その言葉は、私の心に深く刻まれました。「大志を抱く」とは、単に成功を目指すということではありません。人生の意味を探求し、社会に貢献する志を持つこと。そう私は理解しました。
クラーク博士の生き方そのものが、キリスト教の教えを体現しているように感じられました。博士は、日々の行動を通して「神の愛」を実践していたのです。
ある日、私はクラーク博士に尋ねました。
「先生、なぜそんなに熱心に私たちを教えてくださるのですか?」
クラーク博士は優しく微笑んで答えました。
「それは、神の愛のためだよ。神は私たち一人一人を愛しておられる。だから私も、その愛を皆さんに伝えたいんだ」
その言葉に、私は深く感銘を受けました。そして、キリスト教への興味がさらに強くなっていったのです。
しかし、同時に葛藤もありました。日本の伝統的な価値観と、キリスト教の教えをどう調和させるべきか。それは簡単な問題ではありませんでした。
ある晩、同級生の山田(仮名)と夜遅くまで議論しました。
「内村、お前は本当にキリスト教を信じるつもりなのか?」と山田は尋ねました。
「まだ分からない」と私は正直に答えました。「でも、この教えには真理があると感じているんだ」
山田は少し考えてから言いました。「俺には理解できないが、お前がそう感じているのなら、それでいいんじゃないか。ただ、日本人としての誇りは忘れるなよ」
その言葉に、私は大きな励みを感じました。信仰の道は個人的なものであり、他人に強制されるものではない。しかし同時に、自分のルーツを忘れてはいけない。その両方の大切さを、私は学んだのです。
第4章 洗礼と新たな人生
札幌農学校での学びを通じて、私は次第にキリスト教の教えに惹かれていきました。そして、20歳のときに大きな決断をしました。洗礼を受け、クリスチャンになったのです。
洗礼を受けた日、私の心は喜びと希望で満ちあふれていました。「これからは、神の愛に導かれて生きていこう」そう決意したのです。
洗礼式の後、私は静かな場所で一人祈りました。
「神様、私はまだ未熟で、多くの疑問を抱えています。でも、あなたの愛を信じ、その導きに従って生きていきたいと思います。どうか、私を導いてください」
その瞬間、心に深い平安が訪れるのを感じました。
しかし、その決意は同時に、新たな苦悩の始まりでもありました。当時の日本では、キリスト教はまだ広く受け入れられていませんでした。家族や友人の中には、私の選択を理解できない人もいました。
ある日、幼なじみの太郎が私を訪ねてきました。
「鑑三、本当に洗礼を受けたって本当か?」
太郎の目には、悲しみと怒りが混ざっているように見えました。
「ああ、本当だ」と私は答えました。「これが私の選んだ道なんだ」
太郎は苦々しい表情で言いました。「でも、それじゃあお前は日本人じゃなくなってしまうんじゃないのか?」
その言葉に、私は一瞬言葉を失いました。しかし、すぐに気持ちを立て直し、こう答えました。
「違うんだ、太郎。私はむしろ、より良い日本人になりたいんだ。キリスト教の教えを通じて、日本をより良い国にしていきたいんだ」
太郎は黙って私の言葉を聞いていましたが、最後にはこう言って帰っていきました。
「よくわからないが、お前の決意は伝わった。頑張れよ」
この会話は、私にとって大きな励みとなりました。同時に、これからの道のりが決して平坦ではないことを、改めて実感させられたのです。
家族との関係も難しくなりました。特に父は、私の決断を受け入れるのに時間がかかりました。
「鑑三、お前は家の伝統を捨てるつもりか?」と父は厳しい口調で言いました。
「いいえ、父上」と私は答えました。「私は家の伝統を大切にしています。ただ、新しい信仰を通じて、その伝統をより深く理解し、実践していきたいのです」
父は長い間黙っていましたが、最後にはこう言ってくれました。
「お前の決意は分かった。自分の信じる道を歩め。ただし、忘れるな。お前は常に内村家の息子だということをな」
その言葉に、私は深く頭を下げました。父の理解と、家族の絆の大切さを、改めて感じた瞬間でした。
こうして、私の新しい人生が始まりました。それは喜びと苦悩が入り混じった、決して平坦ではない道のりでした。しかし、信仰と家族の支えがあったからこそ、乗り越えていくことができたのです。
第5章 アメリカへの旅立ち
大学を卒業後、私は新たな挑戦を求めてアメリカへ渡ることを決意しました。1884年、23歳の私は、希望と不安を胸に秘めて船に乗り込みました。
長い船旅の間、私は甲板に立ち、広大な海を眺めながら思いを巡らせました。
「これから何が待っているのだろう」
「本当に自分にできることはあるのだろうか」
そんな不安が心をよぎる一方で、新しい世界への期待も高まっていきました。
船上で知り合った日本人留学生の中村(仮名)と、よく夜遅くまで話をしました。
「内村さん、アメリカに何を求めているんですか?」と中村は尋ねました。
「そうですね…」と私は少し考えてから答えました。「キリスト教の本質を学びたいんです。そして、それを日本にどう活かせるか、考えたいんです」
中村は驚いた様子で言いました。「それは難しそうですね。でも、内村さんならきっとできると思います」
その言葉に、私は勇気づけられました。同時に、責任の重さも感じました。
アメリカに到着すると、そこには想像以上の困難が待っていました。言葉の壁、文化の違い、そして何より、生活のための仕事を見つけることの難しさ。私は、アメリカン・ドリームとは程遠い現実に直面したのです。
ある日、路上で靴磨きをしていた時のことです。一人の紳士が私の前で立ち止まりました。
「君は日本人かね?」と彼は尋ねました。
「はい、そうです」と私は答えました。
「なぜ、こんなところで靴磨きをしているんだ?」
その質問に、私は正直に答えました。
「勉強がしたくてアメリカに来たのですが、お金がなくて…」
すると、その紳士は優しく微笑んで言いました。
「わかった。私の家で働かないか? 食事と寝床は提供する。その代わり、君の話をもっと聞かせてほしい」
その紳士の名前はジュリアス・シーリーといい、アマースト大学の総長でした。シーリー博士との出会いは、私のアメリカでの生活を大きく変えることになりました。
シーリー博士の家で働きながら、私は多くのことを学びました。博士は、単に仕事を与えてくれただけでなく、アメリカの文化や思想について深く教えてくれました。
ある晩、夕食後にシーリー博士と話をしていた時のことです。
「内村君、君は日本とアメリカの違いをどう感じているかね?」と博士は尋ねました。
私は少し考えてから答えました。「両国には多くの違いがありますが、人々の心の奥底にある善意は同じだと感じています。ただ、その表現の仕方が異なるのだと思います」
シーリー博士は満足そうに頷きました。「その通りだ。文化は違えども、人間の本質は同じなのだ。その視点を忘れずにいてほしい」
この会話は、私の異文化理解に大きな影響を与えました。違いを認めつつも、共通点を見出す。それが、真の国際理解につながるのだと学んだのです。
第6章 信仰の試練
シーリー博士の助けもあり、私はアマースト大学で学ぶ機会を得ました。そこで私は、西洋の哲学や科学を深く学びました。新しい知識を得ることは刺激的でしたが、同時に大きな疑問も湧いてきたのです。
「科学の発展は、本当に人々を幸せにしているのだろうか?」
「物質的な豊かさは、心の満足につながるのだろうか?」
そんな疑問を抱えながら、私は次第に精神的な危機に陥っていきました。信仰さえも、揺らぎ始めたのです。
ある日の講義後、私は恩師のジョン・スミス教授(仮名)に相談しました。
「先生、私は混乱しています。科学が発展すればするほど、神の存在が遠のいていくように感じるのです」
スミス教授は静かに私の話を聞いてから、こう答えました。
「内村君、それは多くの人が経験する葛藤だ。しかし、科学と信仰は必ずしも相反するものではない。むしろ、科学は神の創造の素晴らしさを理解する手段になり得るんだ」
その言葉に、私は新たな視点を得ました。しかし、心の奥底にある不安は完全には消えませんでした。
ある夜、私は眠れずにキャンパスを歩いていました。星空を見上げながら、心の中で叫んでいました。
「神様、本当にいるのですか? いるなら、私に答えてください」
その時です。突然、心の中に静かな声が聞こえてきたのです。
「わたしはここにいる。恐れるな」
その瞬間、私の心に深い平安が訪れました。それは言葉では表現できないような、深い慰めと喜びでした。
翌日、私はスミス教授にこの体験を話しました。
「先生、昨夜不思議な体験をしました。神様の声を聞いたような…」
スミス教授は優しく微笑んで言いました。
「内村君、それは素晴らしい体験だ。しかし、忘れてはいけない。信仰は、そういった特別な体験だけでなく、日々の生活の中で培われていくものなんだ」
この体験と教授の言葉を通じて、私の信仰は新たな段階に入りました。科学や哲学の知識と、信仰は決して相反するものではない。むしろ、それらを調和させることで、より深い真理に近づけるのではないか。そう考えるようになったのです。
その後の私の研究や思索は、この新たな視点に基づいて進められていきました。科学的な探究と信仰的な洞察を融合させることで、より包括的な世界観を構築しようと試みたのです。
この時期の経験は、後の私の著作や講演に大きな影響を与えることになりました。科学と信仰の調和、理性と感性のバランス、これらのテーマは、生涯を通じて私が探求し続けたものとなったのです。
第7章 日本への帰国
アメリカでの学びを終え、1888年、私は日本に帰国しました。しかし、待っていたのは厳しい現実でした。キリスト教への風当たりは、以前にも増して強くなっていたのです。
帰国直後、私は東京の教会で講演する機会を得ました。そこで私は、アメリカでの経験と、科学と信仰の調和について語りました。しかし、聴衆の反応は冷ややかでした。
講演後、一人の年配の男性が私に近づいてきました。
「若い者よ、西洋かぶれして日本の伝統を忘れてしまったのか?」
その言葉に、私は深く傷つきました。しかし、冷静に答えようと努めました。
「いいえ、決してそうではありません。むしろ、日本の伝統とキリスト教の教えを融合させることで、新しい価値を生み出せると信じているのです」
男性は不満そうな表情を浮かべたまま立ち去りましたが、この出来事は私に大きな課題を突きつけました。いかにして西洋の思想と日本の伝統を調和させるか。それは、これからの私の人生における中心的なテーマとなったのです。
ある日、私は母校の札幌農学校で講演する機会を得ました。テーマは「なぜ私はキリスト教徒になったか」。会場には、好奇心から来た学生たちだけでなく、批判的な目を向ける人々も多くいました。
講演が始まると、会場には緊張感が漂いました。私は深呼吸をして、話し始めました。
「私がキリスト教に出会ったのは、真理を求める旅の途中でした。それは、日本の伝統を捨てることではありません。むしろ、日本の精神とキリスト教の教えを融合させることで、新たな価値を生み出せると信じています」
講演の途中、ある学生が立ち上がって叫びました。
「でも、それは日本の伝統を裏切ることじゃないですか!」
会場がざわつく中、私は静かに答えました。
「伝統を大切にすることと、新しい考えを受け入れることは、決して矛盾しません。むしろ、両者を調和させることで、より豊かな文化が生まれるのです」
その言葉に、会場は静まり返りました。講演後、多くの学生たちが私のもとを訪れ、さまざまな質問をしてくれました。その中には、批判的だった学生も含まれていました。
「先生の言葉、よく分かりませんでした。でも、もっと聞いてみたいです」
その言葉に、私は希望を感じました。対話を通じて、互いの理解を深めていける。そう確信したのです。
この講演をきっかけに、私は日本各地で講演活動を行うようになりました。そこでは、キリスト教の教えと日本の伝統的な価値観をいかに調和させるか、という問題について熱心に語りました。
ある地方都市での講演後、一人の若い教師が私に質問しました。
「内村先生、キリスト教と武士道は共存できるのでしょうか?」
私はこう答えました。「武士道の精神、特に誠実さや自己犠牲の精神は、キリスト教の教えと多くの共通点があります。両者を深く理解することで、より高い倫理観を築くことができるのです」
この答えに、若い教師は深く頷きました。「そう考えると、新しい可能性が見えてきますね」
このような対話を重ねることで、私は自分の思想をより深め、洗練させていきました。同時に、多くの人々の心に、新しい視点を植え付けることができたのです。
第8章 不敬事件と苦難の日々
1891年、私の人生に大きな転機が訪れました。それは「不敬事件」と呼ばれる出来事です。
当時、私は第一高等中学校(現在の東京大学教養学部の前身)で教鞭を執っていました。ある日、教育勅語に対する最敬礼の際、私は頭を下げることを拒否しました。それは、私の信仰と良心に基づく行動でした。
この行動は、すぐに大きな騒動となりました。新聞は私を「不敬漢」と呼び、批判の声が巻き起こりました。
学校の同僚たちは、私を避けるようになりました。廊下ですれ違っても、目を合わせようとしません。ある日、一人の同僚が私に近づいてきました。
「内村君、君の行動は理解できる。でも、もう少し周りのことも考えてくれないか」
その言葉に、私は深く考え込みました。自分の信念を貫くことと、周囲への配慮のバランスをどう取るべきか。それは簡単な問題ではありませんでした。
結局、私は教職を辞することを決意しました。それは、学校や生徒たちに迷惑をかけたくないという思いからでした。
辞職後、私は経済的にも精神的にも苦しい日々を過ごしました。しかし、この経験は私の信仰をさらに深めることになりました。
ある夜、私は自宅で聖書を読んでいました。そこに、妻の加寿子が静かに近づいてきました。
「あなた、後悔していませんか?」
私は聖書から目を上げ、加寿子の目を見つめました。
「いいえ、後悔はしていない。ただ、もっと賢明な方法があったかもしれないと思うことはある」
加寿子は優しく微笑んで言いました。
「あなたの信念を尊敬します。これからも、あなたの側にいます」
その言葉に、私は深い慰めを感じました。同時に、これからの人生をどう歩んでいくべきか、真剣に考えるきっかけとなりました。
この経験を通じて、私は「無教会主義」という考えに至りました。組織化された教会ではなく、個人の内なる信仰こそが大切だという考えです。
不敬事件後、私は執筆活動に力を入れるようになりました。自分の思想や信仰を、より多くの人々に伝えたいと考えたのです。
この時期に書いた『キリスト教問答』は、多くの人々の心に響きました。ある読者から手紙が届きました。
「内村先生、あなたの本を読んで、初めてキリスト教の本質が分かりました。ありがとうございます」
その言葉に、私は大きな励みを感じました。苦難の中にあっても、自分の使命を果たすことができる。そう確信したのです。
第9章 『代表的日本人』の執筆
1908年、私は『代表的日本人』という本を書きました。この本で私は、日本の偉人たちの生涯を通して、日本人の精神性を世界に伝えようと試みたのです。
西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮。これらの人物の生き方を通じて、日本人の魂の深さを描き出そうとしました。
本の執筆中、私はある夜、書斎で深い考えに沈んでいました。そこへ、妻の加寿子が静かに入ってきました。
「あなた、もう遅いわ。少し休んだら?」
私は疲れた目を上げて、加寿子に微笑みかけました。
「ありがとう。でも、この本には大切な使命があるんだ。日本と西洋の架け橋になれるかもしれない」
加寿子はしばらく黙って私の顔を見つめていました。そして、こう言いました。
「分かったわ。でも、無理はしないでね。あなたの健康が一番大切だから」
その言葉に、私は深く感動しました。加寿子の支えがあったからこそ、この大事業を成し遂げられたのだと実感したのです。
執筆の過程で、私は改めて日本の文化や歴史の深さを実感しました。同時に、それを世界に伝えることの難しさも感じました。
ある日、私は執筆の合間に、弟子の一人である田中(仮名)と話をしていました。
「先生、なぜ日本人の精神性を外国人に伝えようとするのですか?」
私はこう答えました。「日本と世界が真の意味で理解し合うためには、互いの精神性を知ることが不可欠だからだ。そして、それは世界平和につながるのだ」
田中は深く頷きました。「分かりました。私も、先生の志を継いでいきたいと思います」
その言葉に、私は大きな喜びを感じました。自分の思想が次の世代に受け継がれていく。それは、教育者として最大の幸せでした。
『代表的日本人』は、海外で大きな反響を呼びました。多くの外国人が、この本を通じて初めて日本の精神性の深さを知ったのです。
ある日、アメリカの友人から手紙が届きました。
「内村さん、あなたの本を読みました。日本人の魂の美しさに感動しました。これからは、日本をもっと理解しようと思います」
その言葉に、私は大きな喜びを感じました。文化の違いを超えて、人々の心に届く言葉を書くことができた。それは、私の長年の夢の実現でもあったのです。
この本の成功は、私に新たな使命感を与えました。日本と世界の架け橋となること。それは、私の残りの人生をかけて取り組むべき課題だと感じたのです。
第10章 晩年と遺志
年を重ねるにつれ、私の体力は衰えていきました。しかし、真理を求める情熱は少しも衰えることはありませんでした。
1930年、私は最後の大きな仕事として、『聖書注解』の執筆に取り掛かりました。これは、聖書の言葉を日本人の視点から解説する大作でした。
ある日、私は自宅の庭で、若い弟子たちと語り合っていました。桜の木の下で、穏やかな春の日差しを浴びながらの談話は、私にとって至福の時間でした。
「先生、なぜそんなに一生懸命に書き続けるのですか?」と、一人の弟子が尋ねました。
私は空を見上げながら答えました。
「それはね、まだ伝えきれていないことがたくさんあるからだよ。この命ある限り、真理を求め続けたい。そして、それを次の世代に伝えていきたいんだ」
弟子たちは、真剣な表情で私の言葉に耳を傾けていました。
別の弟子が質問しました。「先生は、自分の人生に満足していますか?」
私はしばらく考えてから答えました。
「満足というよりは、感謝している。多くの困難もあったが、それらを通して成長できた。そして、素晴らしい出会いにも恵まれた。人生は神からの贈り物だ。それを精一杯生きることが、私たちの使命なのだよ」
その言葉に、弟子たちは深く頷きました。
晩年の私は、若い世代への教育にも力を入れました。毎週日曜日には、自宅で聖書研究会を開いていました。そこには、様々な背景を持つ若者たちが集まってきました。
ある日の研究会で、一人の若い女性が質問しました。
「内村先生、これからの日本はどうなると思いますか?」
私はこう答えました。「日本の未来は、君たち若い世代にかかっている。物質的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさを追求してほしい。そして、日本の良さを保ちながらも、世界に開かれた心を持ってほしい」
その言葉に、参加者たちは真剣な表情で聞き入っていました。
そして1930年3月28日、私は69歳でこの世を去りました。最期の瞬間まで、私は聖書を手放すことはありませんでした。
私の葬儀には、多くの人々が参列しました。キリスト教徒だけでなく、さまざまな信仰を持つ人々、そして私の思想に影響を受けた若者たちも集まってきました。
ある参列者がこう語りました。
「内村先生は、信仰の自由と知的探求の大切さを教えてくれました。その教えは、これからも多くの人々の心に生き続けるでしょう」
私の人生は、決して平坦なものではありませんでした。しかし、真理を求め続けた日々は、かけがえのない宝物でした。そして、その探求の旅は、私の死後も、多くの人々によって受け継がれていくのです。
エピローグ
私、内村鑑三の物語はここで終わります。しかし、真理を求める旅は、決して終わることはありません。
皆さんへ、最後のメッセージを贈ります。
「真理を愛し、自由に考え、そして勇気を持って行動してください。たとえ困難があっても、自分の信じる道を歩み続けてください。そうすれば、必ず道は開けるはずです」
私の人生を振り返ると、多くの挑戦と困難がありました。しかし、それらの経験を通して、私は成長し、自分の信念を深めることができました。
キリスト教との出会い、アメリカでの留学、不敬事件、そして晩年の執筆活動。これらの経験は全て、私を形作る重要な要素となりました。
特に、日本の伝統とキリスト教の教えを調和させようとする試みは、私の生涯を通じての大きなテーマでした。それは簡単な道のりではありませんでしたが、その過程で、私は日本と世界の架け橋となる新しい思想を生み出すことができたと信じています。
若い皆さんへ。世界は常に変化し、新しい課題が生まれています。しかし、真理の探求という人間の根本的な営みは、時代が変わっても変わりません。
自分の目で見、自分の頭で考え、そして自分の心で感じてください。他人の意見を鵜呑みにせず、しかし謙虚に学ぶ姿勢を忘れないでください。
そして、自分の信じる道を歩む勇気を持ってください。たとえ周囲の理解が得られなくても、自分の良心に従って行動することが大切です。ただし、それは独善ではありません。常に自己を省み、他者の意見に耳を傾ける謙虚さも必要です。
最後に、愛することを忘れないでください。神を愛し、人を愛し、そして真理を愛する。それが、人生の最も大切な要素だと私は信じています。
この物語が、皆さんの人生の何かのヒントになれば幸いです。真理の探求者として、共に歩んでいきましょう。
皆さんの人生が、祝福に満ちたものになりますように。
(おわり)