第一章:孤独な始まり
私の人生は、1643年のクリスマスの朝、英国リンカンシャー州ウールズソープの小さな農家で始まった。父は私が生まれる前に他界し、母は私を未熟児として産んだ。当時、誰もが私の生存を疑っていたという。

「アイザック、強くなるのよ」
祖母の声が、幼い私の耳に響く。彼女の温かい手が、私の小さな体を包み込む。生まれてすぐの記憶などあるはずもないが、私の人生はこの瞬間から、孤独との闘いだったのかもしれない。
冬の寒さが厳しい日々、祖母は私を暖炉のそばに寝かせ、優しく子守唄を歌ってくれた。その歌声は、今でも心の奥底に残っている。

「お前は特別な子よ、アイザック。きっと大きな事を成し遂げるわ」
祖母の言葉は、まるで予言のようだった。当時の私には、その意味がわからなかったが、後年になって、その言葉の重みを実感することになる。
3歳の時、母は再婚した。継父のバーナバス・スミスとの新しい生活が始まり、私は祖母の元で育てられることになった。母の愛情が欲しかった。だが、それは叶わぬ願いだった。
「母さん、僕と一緒に住んでくれないの?」
別れ際、私は母の袖を引っ張った。母は悲しそうな顔で私を見つめ、こう言った。
「アイザック、あなたはここで幸せになるのよ。私はあなたのことを忘れないわ」
その言葉は、幼い私の心に深い傷を残した。なぜ母は私を置いていくのか。その疑問は、長年私の心を苛み続けた。
祖母の家での生活は、静かで穏やかだった。広々とした庭には、たくさんの木々が生い茂り、小川がさらさらと流れていた。私はよくその庭で一人遊びをした。
木の枝で作った簡単な水車を小川に浮かべ、その動きを観察するのが好きだった。水の流れ、風の動き、太陽の光。自然の中に身を置くと、不思議と心が落ち着いた。

「アイザック、また本を読んでいるのか?」
ある日、祖母が私の部屋に入ってきた。8歳になっていた私は、一人で本を読むのが日課だった。
「はい、おばあちゃん。この本に書いてある星の動きが面白くて…」
「そうかい。お前は本当に賢い子だね」
祖母は優しく微笑んだが、その目には少しの寂しさが浮かんでいた。私にはそれがわかった。私の孤独は、周りの人々の孤独でもあったのだ。
夜になると、私はよく屋根裏部屋に忍び込んで、小さな窓から星空を眺めた。無数の星が輝く夜空を見上げながら、宇宙の広大さに思いを馳せた。

「あの星々は、どうやって動いているんだろう。なぜあんなにも美しく輝いているんだろう」
そんな疑問が、幼い私の心を満たしていった。後に、この純粋な好奇心が、私を科学の世界へと導くことになる。
第二章:学びの日々
11歳になった私は、グランサム・スクールに入学した。そこで初めて、同年代の子供たちと触れ合うことになった。しかし、私の内向的な性格と知的好奇心は、すぐに他の生徒たちの標的となった。
入学初日、教室に入ると、皆が私を珍しそうに見つめていた。

「君が新入生のニュートンか。随分小さいねえ」
クラスの級長らしき少年が、からかうように言った。確かに、私は年齢の割に小柄だった。
「は、はい…」
私は小さな声で答えた。その瞬間、教室中が笑いに包まれた。顔が熱くなるのを感じながら、私は急いで席に着いた。
授業が始まると、状況は一変した。先生の質問に、私はすらすらと答えていった。特に、数学の時間には、他の生徒が苦戦する問題も、すぐに解いてしまった。
「素晴らしい、ニュートン君!」
先生は感心した様子で私を褒めた。しかし、クラスメイトたちの視線は冷たくなるばかりだった。
休み時間、私はいつも一人で過ごした。校庭の片隅で本を読んでいると、クラスメイトのトムが近づいてきた。
「おい、ニュートン!また一人で何してるんだ?」
トムが、私の肩を強く叩いた。私は黙って肩をすくめるだけだった。
「返事くらいしろよ!」
トムは怒り、私の本を床に叩きつけた。その瞬間、何かが私の中で燃え上がった。
「やめろ!」
私は叫び、トムに飛びかかった。予想外の反撃に、トムは驚いた顔をした。

二人で取っ組み合いになったところで、先生が駆けつけてきた。
「何をしている!二人とも校長室へ来なさい」
私たちは、肩を落として校長室へ向かった。
校長室で、ストークス先生は厳しい表情で私たちを見つめていた。
「喧嘩をするとはいけませんね。特に君、ニュートン君。君のような優秀な生徒が…」
「でも先生、トムが僕の本を…」
私は必死で弁解しようとした。
「わかっているよ。トム君も反省しているはずだ。ところで、君が読んでいた本は何かな?」
「ユークリッドの『原論』です」
ストークス先生の目が輝いた。
「おや、それは難しい本だね。よく理解できているのかい?」
「はい、面白いです。特に幾何学の証明が…」
私は熱心に説明を始めた。ストークス先生は驚きの表情を隠せなかった。
「君には特別な才能がある。それを大切にしなさい」
その言葉が、私の人生を変えた。それからというもの、私は勉強に没頭した。いじめっ子だったトムさえ、次第に私を認めるようになった。
「ねえ、ニュートン。この問題、教えてくれないか」
ある日、トムが恥ずかしそうに私に話しかけてきた。最初は戸惑ったが、私は彼に数学を教え始めた。
「へえ、こうやって考えるのか。お前、本当に頭いいんだな」
トムは感心したように言った。それ以来、彼は私を守るようになり、他の生徒たちも少しずつ私を受け入れてくれるようになった。
学校生活は徐々に楽しくなっていった。授業では常にトップの成績を維持し、先生方からの信頼も厚くなった。しかし、私の興味は教科書の内容だけにとどまらなかった。
放課後、私はよく学校の裏庭で実験をしていた。太陽の光を使って影の長さを測定したり、風車の羽根の形を変えて回転速度を比較したり。

「また変わったことをしているね、アイザック」
ある日、ストークス先生が私の実験を見つけた。
「はい、風の力について調べているんです」
「なるほど。君の好奇心は尽きないようだね。その探究心を大切にしなさい。いつか、大きな発見につながるかもしれないよ」
ストークス先生の言葉は、私の心に深く刻まれた。この頃から、私は自然界の謎を解き明かすことが、自分の使命なのではないかと考え始めていた。
第三章:ケンブリッジへの道
18歳になった私は、ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに入学した。そこで、私の人生は大きく開けた。
大学の門をくぐった時、私の胸は期待と不安で一杯だった。広大なキャンパス、荘厳な建物群。そこには、私がこれまで想像もしなかった知の世界が広がっていた。

「ようこそ、トリニティ・カレッジへ」
入学式で学長が述べた言葉が、今でも耳に残っている。
「諸君は、これから真理の探究という壮大な冒険に出発するのだ。恐れることはない。好奇心と探究心を武器に、未知の領域に果敢に挑戦してほしい」
その言葉に、私は身が引き締まる思いがした。
大学での生活は、想像以上に刺激的だった。lectures(講義)では、当時の最先端の知識に触れることができた。特に、数学と自然哲学(現代の物理学に相当)の講義は、私にとって目から鱗が落ちる体験の連続だった。
「ニュートン君、講義の内容はどうかね?」
ある日、指導教官のアイザック・バロウ博士が私に声をかけた。
「はい、とても興味深いです。特に、ケプラーの惑星運動の法則には感銘を受けました」
「そうか。君なら、もっと深く掘り下げることができるはずだ。これらの本を読んでみたまえ」
バロウ博士は、いくつかの専門書を私に手渡した。その中には、ガリレオやデカルトの著作もあった。
「ありがとうございます。でも、まだまだ分からないことばかりで…」
「それが大切なんだ。分からないことに挑戦し続けることが、新しい発見につながる」
バロウ博士の言葉に、私は大きくうなずいた。
それからというもの、私は寝る間も惜しんで勉強に打ち込んだ。図書館に籠もり、夜遅くまで本を読みふける日々が続いた。時には、朝日が昇るまで机に向かっていることもあった。

同級生たちが酒場で騒いでいる間も、私は自室で計算に没頭していた。ある友人は私のことを「変わり者」と呼んだが、私にはそんなことを気にする暇はなかった。
「ニュートン君、君の数学の才能は驚くべきものだ」
2年生の終わりころ、バロウ博士が私をオフィスに呼んだ。
「ありがとうございます。でも、まだまだ分からないことばかりで…」
「謙遜する必要はないよ。君の論文は、多くの教授たちを驚かせた。特に、君の二項定理の証明は見事だった」
バロウ博士の言葉に、私は嬉しさと同時に、大きな責任を感じた。
「これからも頑張ります」
「期待しているよ、アイザック。君には、この大学の、いや、この国の科学を変える力がある」
バロウ博士の言葉は、私の背中を押してくれた。しかし、その直後、予期せぬ事態が起こる。
1665年、ロンドンで始まったペストの大流行が、ケンブリッジにも及んだのだ。大学は閉鎖され、学生たちは帰郷を余儀なくされた。
「一時的な措置だ。落ち着いたらすぐに大学に戻ってこい」
バロウ博士はそう言って、私を送り出した。しかし、この「一時的な措置」が、私の人生を大きく変えることになるとは、誰も予想していなかった。
私は故郷のウールズソープに戻ることになった。そこで過ごした2年間が、私の人生を決定づけることになる。
第四章:革命的発見の日々
ウールズソープに戻った私は、最初こそ落胆していた。大学での研究を中断せざるを得なくなったからだ。しかし、この田舎での日々が、後に私の最も実り多き時期となるとは、誰が想像しただろうか。
祖母の家には広い庭があり、そこで私は自由に思考を巡らせることができた。ある秋の午後、リンゴの木の下で休んでいたとき、一つのリンゴが落ちるのを見た。

「なぜリンゴは必ず地面に落ちるのだろう?」
この素朴な疑問が、後の万有引力の法則につながることになる。リンゴが落ちる様子を何度も観察しているうちに、ある考えが浮かんだ。
「もしかして、リンゴを地面に引き寄せる力と、月を地球の周りに引き留める力は、同じものなのではないか?」
この閃きに、私は震えるほど興奮した。すぐに部屋に戻り、計算を始めた。夜が明けるまで、私は寝食を忘れて計算に没頭した。
「アイザック、また徹夜したの?」
朝、心配そうな顔で部屋に入ってきた母に、私は興奮気味に説明した。
「母さん、僕は大変なことを発見したんだ!宇宙のすべての物体は、お互いを引き寄せ合っているんだ!」
母は困惑した表情を浮かべたが、優しく微笑んでくれた。
「そう…よくわからないけど、あなたにとって大切なことなのね」
母は黙ってうなずき、温かい食事を置いていってくれた。
同時期、私は光の性質についても考えを巡らせていた。大学から持ち帰った三角プリズムを使って、太陽光の分光実験を行った。
暗い部屋の中で、小さな穴から差し込む太陽光をプリズムに当てると、美しい虹色のスペクトルが壁に映し出された。

「なんと美しい…」
私は息を呑んだ。この実験を何度も繰り返すうちに、ある重要な発見にたどり着いた。
「白色光は、実は様々な色の光が混ざったものなのだ!」
この発見は、後に光学の分野に革命を起こすことになる。
夜遅くまで実験を続ける私を、母は心配そうに見ていた。
「アイザック、体を壊さないでね」
「大丈夫だよ、母さん。これは僕にとってとても大切なんだ」
母は黙ってうなずき、また温かい食事を置いていってくれた。母の静かな支えが、私の研究を後押ししてくれていたのだと、今になって思う。
この2年間、私は数学、物理学、光学の分野で、次々と新しい発見をしていった。微分積分学の基礎となる考えも、この時期に生まれた。
しかし、これらの発見のほとんどは、当時は誰にも知られることはなかった。私は自分の考えを書き留めはしたが、発表する機会も、その自信もなかったのだ。
1667年、ようやくペストの危機が去り、私はケンブリッジに戻ることができた。
第五章:栄光と論争
ケンブリッジに戻った私を、バロウ博士は温かく迎えてくれた。
「アイザック、元気だったかい?この2年間、何か新しい発見はあったかね?」
私は躊躇した。自分の発見を話すべきか迷ったのだ。しかし、バロウ博士の励ましに、少しずつ自分の考えを打ち明けた。
博士の目が驚きで見開かれていくのがわかった。
「これは…素晴らしい!アイザック、君はこの2年間で、科学の歴史を変えるような発見をしているんだよ!」
バロウ博士の後押しもあり、私は少しずつ自分の研究を発表し始めた。特に、光学の分野での発見は大きな反響を呼んだ。
1669年、バロウ博士が数学の教授職を退き、その後任として私を推薦してくれた。わずか26歳でのことだった。
「君こそが、この職にふさわしい。私よりもずっと優秀だからね」
バロウ博士はそう言って、私の肩を叩いてくれた。
教授となった私は、自分の研究にさらに没頭した。講義では、自分の発見や理論を学生たちに教えた。しかし、多くの学生には難しすぎたようで、講義室はしばしばがらんとしていた。

研究に没頭するあまり、体調を崩すこともあった。ある時などは、3日間部屋に籠もりきりで、食事も取らずに計算に没頭していた。

「ニュートン、体を大切にしないとダメだよ」
同僚のエドモンド・ハレーが心配そうに言った。このハレーとの出会いが、私の人生を大きく変えることになる。
1684年、ハレーが私を訪ねてきた。
「ニュートン、君に聞きたいことがあるんだ。惑星の軌道はどんな形をしていると思う?」
「楕円だろう」と私は即答した。
「その通り!でも、なぜ楕円なんだ?証明できるかい?」
私は少し考え、こう答えた。「3か月ほど時間をくれ」
実際には3か月どころか、2年の歳月を要することになった。しかし、この挑戦が、私の主著『自然哲学の数学的原理』(通称:プリンキピア)の執筆につながったのだ。
1687年、ついにプリンキピアを出版した。この本で私は、万有引力の法則を含む、運動の3法則を提示した。これらの法則は、地上の物体の運動から天体の運動まで、すべての物体の動きを統一的に説明するものだった。

「これはすごい!ニュートン、君は科学の歴史を変えたんだ!」
出版後、ハレーは興奮して私の研究室に飛び込んできた。
彼の言葉通り、プリンキピアは科学界に衝撃を与えた。多くの科学者がその内容に感銘を受け、私の名は一躍有名になった。
しかし、栄光と同時に、論争も始まった。特に、微積分の発見を巡って、ドイツの数学者ゴットフリート・ライプニッツとの論争は熾烈を極めた。
「ニュートン、君とライプニッツ、どちらが先に微積分を発見したのか?」
1699年、王立協会の会合で、この質問が投げかけられた。
「私です。証拠もあります」
私は自信を持って答えた。しかし、心の中では複雑な思いが渦巻いていた。真理の探究が、こんな醜い争いを生むとは…
この論争は、私の晩年まで尾を引くことになる。
第六章:晩年の光と影
科学者としての名声は確立したものの、私の探究心は尽きることがなかった。特に、宗教と錬金術への関心は深まるばかりだった。
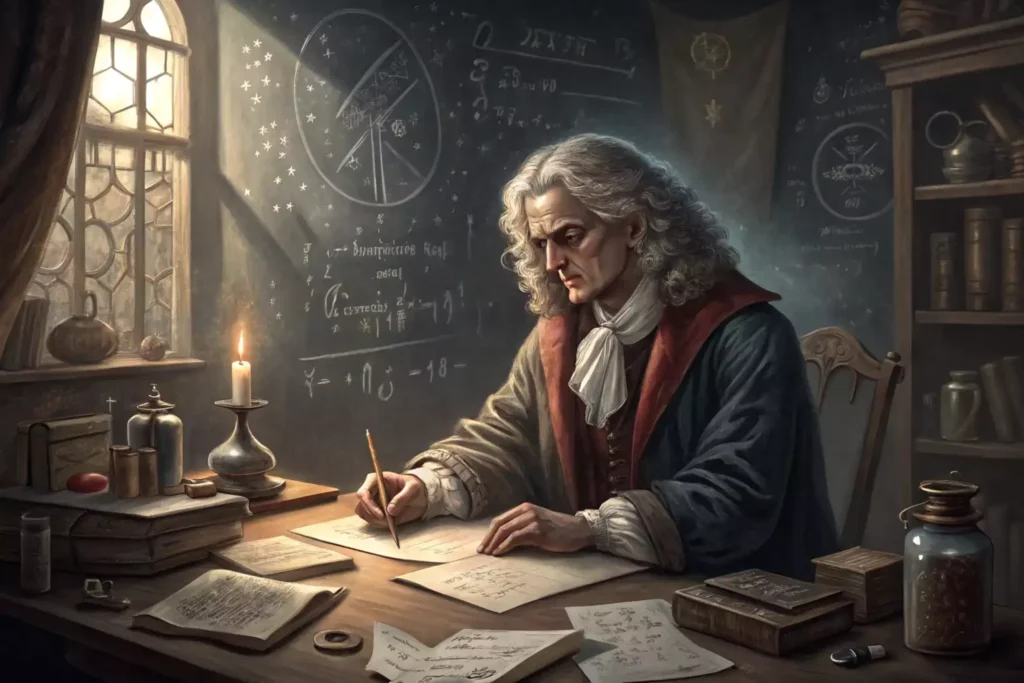
「ニュートン卿、あなたはなぜ錬金術に興味を持つのですか?」
ある日、若い学生が尋ねてきた。
「宇宙の真理は、目に見えるものだけではないからだよ」
私はそう答えたが、本当の理由を言葉にすることは難しかった。それは、孤独な少年時代から続く、存在の意味への問いだったのかもしれない。
1696年、私はロンドンに移り、造幣局長官として国家に仕えることになった。

科学研究からは少し離れることになったが、この職務にも真剣に取り組んだ。当時、偽造硬貨が蔓延しており、その対策に奔走した。
「偽造者たちを徹底的に取り締まるんだ」
私は部下たちにそう指示した。厳しい取り締まりの結果、何人もの偽造者が処刑されることになった。この経験は、私の心に暗い影を落とした。
晩年、私は『ダニエル書の予言』や『ヨハネの黙示録』の研究に没頭した。宇宙の秩序を解明した自分にも、まだ理解できないことがあると感じていたのだ。

「光は粒子であり、同時に波でもある…」
最後まで、光の本質を追い求め続けた私。その探究心こそが、私の人生そのものだったのかもしれない。

1727年3月20日、私の84年の生涯は幕を閉じた。最期のときまで、私は宇宙の真理を求め続けた。

エピローグ:永遠の光へ
私の人生を振り返ると、それは光と影の狭間を彷徨う旅だったように思う。
孤独な少年は、宇宙の法則を解き明かす科学者となった。しかし、その心の奥底にあった問いは、最後まで解けないままだった。
私の遺した理論や発見は、後世の科学者たちによって更に発展させられていくだろう。そして、彼らもまた、新たな謎に直面し、その解明に人生を捧げることだろう。
これが科学という営みなのだ。永遠に続く、光を求める旅。私の人生は終わったが、その光は決して消えることはない。
後世の人々よ、好奇心を持ち続けたまえ。疑問を抱き、探究することを恐れてはいけない。なぜなら、真理の探究こそが、人類を前進させる原動力なのだから。































































































































