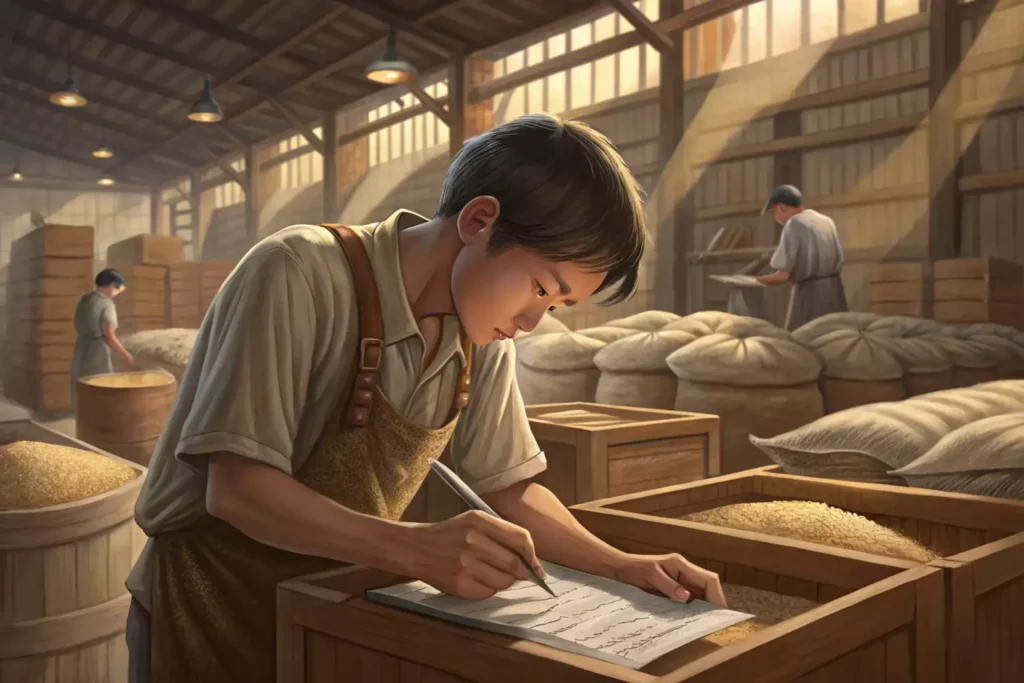
第一章:幼少期の学び
私の名は孔丘、字は仲尼。後世の人々には孔子として知られることになりました。紀元前551年、魯の国の昌平郷曲阜の地に生まれました。私の人生は、学びと教えの旅でした。
生まれた時代は、春秋時代と呼ばれる激動の時代でした。周王朝の権威が衰え、諸侯国が互いに争い合う世の中でした。そんな中で、私は小さな命として世に生を受けたのです。
幼い頃から、私は好奇心旺盛な子供でした。父の叔梁紇は私が3歳の時に亡くなり、母の顔徵在が私を育ててくれました。父との思い出はほとんどありませんが、母はよく父のことを話してくれました。
「お前の父は、正義感の強い人だった。困っている人を見れば、必ず手を差し伸べていたんだよ」
母の言葉を聞くたびに、私は父のような人間になりたいと思いました。
貧しい暮らしでしたが、母は私の教育に熱心でした。毎日、母は私に文字を教え、礼儀作法を厳しく躾けました。

「丘よ、学ぶことを忘れてはいけないよ。知識こそが人を高める。そして、礼を知ることが、人を人たらしめるのだ」
母の言葉は、私の心に深く刻まれました。6歳の時、近所に住む老人から更に進んだ文字と古典の初歩を教わりました。その老人の名は王叔でした。
「孔丘、お前は聡明な子だ。文字を覚えれば、世界が広がるぞ。古の聖人の言葉を学べば、人としての道が見えてくる」
王叔の教えは、単なる知識の伝達ではありませんでした。彼は文字や古典を通じて、人としての在り方を私に示してくれたのです。
「孔丘、『詩経』を読んでみなさい。そこには人間の喜怒哀楽が詰まっている。人の心を理解することは、世を治める上で最も大切なことだ」
王叔の言葉に励まされ、私は必死に学びました。文字を覚え、古典を読むたびに、新しい世界が開けていくようでした。特に『詩経』の中の言葉は、私の心に深く響きました。
関関雎鳩、在河之洲。窈窕淑女、君子好逑。
(かんかんとなくコウという鳥が、河の中州にいる。たおやかで美しい女性は、君子のよい配偶者である)
この詩の一節を読んだ時、私は人間関係の調和の大切さを感じました。後に、この考えは私の「礼」の思想の基礎となっていきます。
7歳になると、私は村の学校に通い始めました。そこで出会った友人の顔回は、生涯の親友となりました。顔回は私より2歳年下でしたが、その聡明さと学ぶ姿勢に私は感銘を受けました。
「孔丘、君はいつも一生懸命だね。僕も負けないように頑張るよ」
顔回との競い合いは、私の学びをさらに深めてくれました。私たちは互いに切磋琢磨し、時には夜遅くまで議論を交わしました。
「顔回、人として最も大切なものは何だと思う?」
「うーん、難しい質問だね。でも、私は『仁』だと思う。人を思いやり、互いに助け合うこと。それが人間社会の基本じゃないかな」
顔回の答えに、私は深く考えさせられました。この「仁」という概念は、後に私の思想の中心となっていきます。
学校では、六芸と呼ばれる礼、楽、射、御、書、数を学びました。これらは当時の貴族の子弟が身につけるべき教養でした。私は特に「礼」と「楽」に興味を持ちました。
「礼」は単なる形式的な作法ではありません。それは人間関係を円滑にし、社会の秩序を保つための重要な要素です。「楽」もまた、単なる娯楽ではなく、人々の心を調和させ、社会の安定をもたらす力があると私は考えました。
こうして、幼少期の私は、母、王叔、顔回、そして学校での学びを通じて、後の思想の基礎を形成していったのです。貧しい生活の中でも、知識を得ることの喜びと、人としての在り方を学ぶことの大切さを、身をもって体験しました。
この時期の経験が、後の私の教育思想に大きな影響を与えることになります。すべての人に学ぶ機会を与えるべきだという考えは、この時期の体験から生まれたのです。
第二章:青年期の苦悩と決意
15歳になった私は、学問に励む決意を固めました。しかし、現実は厳しく、生活のために様々な仕事をしなければなりませんでした。穀物の管理や家畜の世話など、どんな仕事も真剣に取り組みました。
ある日、私は穀物倉の管理の仕事をしていました。そこで出会った年配の役人が私に声をかけてきました。
「若者よ、お前は丁寧に仕事をしているな。だが、なぜそこまで真剣に取り組むのだ?」
「はい、どんな仕事も大切だと思うからです。穀物を正確に管理することで、人々の生活が支えられるのではないでしょうか」
役人は驚いた様子で私を見つめ、こう言いました。
「お前の考えは正しい。だが、お前にはもっと大きなことができるはずだ。学問を続けなさい。そして、その知恵を世のために使うのだ」
この言葉に、私は深く考えさせられました。確かに、目の前の仕事に真剣に取り組むことは大切です。しかし、それだけでは不十分なのかもしれません。もっと広い視野で世の中を見つめ、人々のために何ができるかを考える必要があるのではないか。
その後、市場で働いていた時のことです。そこで出会った老人が私に声をかけてきました。
「若者よ、お前は何のために働いているのだ?」
「生きるためです」と私は答えました。
老人は微笑んで言いました。「生きるだけではなく、何かのために生きることが大切だ。お前には大きな可能性がある。その力を世のために使いなさい」
この二人との出会いを通じて、私は自分の使命について深く考えるようになりました。単に生きるだけでなく、世の中をよりよくするために生きよう。そう決意したのです。
19歳で結婚し、翌年には息子の鯉が生まれました。家族を養うことの大変さを実感しましたが、それでも学問への情熱は冷めませんでした。夜遅くまで書物を読み、昼間は仕事に励みました。
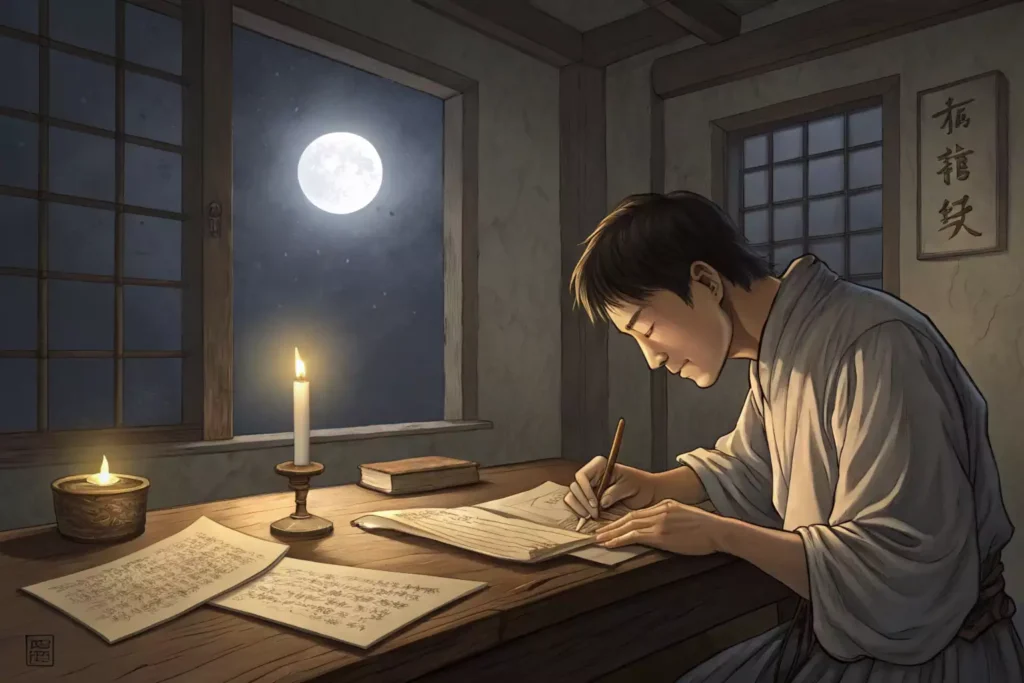
妻の鍾氏は、私の学問への情熱を理解し、支えてくれました。
「あなた、夜遅くまで勉強して体を壊さないでください」
「ありがとう。でも、学ばなければならないことがたくさんあるんだ。この知識が、いつか世の中のためになると信じているんだ」
妻は黙ってうなずき、私の勉強を見守ってくれました。
ある夜、勉強していると、幼い息子の鯉が部屋に入ってきました。
「お父さん、どうしてそんなに勉強するの?」
私は息子を膝の上に座らせ、こう答えました。
「世の中をよりよくするためだよ。勉強すれば、人々を助けることができるんだ。鯉、覚えておきなさい。学ぶことは、自分のためだけではない。それは、周りの人々、そして社会全体のためなんだ」
息子に語りかけながら、私は自分の使命を再確認しました。そして、いつか自分の学んだことを多くの人々に伝えたいという思いが、徐々に強くなっていきました。
20代後半になると、私の評判は少しずつ広まり始めました。私の元には、学びを求める若者たちが集まってくるようになりました。彼らに教えることで、私自身も多くのことを学びました。
「先生、どうすれば良い政治ができるのでしょうか?」ある日、弟子の子貢がそう尋ねてきました。
「子貢よ、良い政治の基本は、民を愛し、民のために尽くすことだ。しかし、それだけでは不十分だ。為政者自身が徳を磨き、模範を示さなければならない」
「では、どうすれば徳を磨けるのでしょうか?」
「学ぶことだ。古の聖人の教えを学び、日々の生活の中で実践することだ。そして、常に自分を省みることを忘れてはならない」
このような対話を通じて、私の思想はより深まっていきました。そして、いつかはこの考えを広く世に伝え、乱れた世の中を正したいという思いが、私の心の中で大きくなっていったのです。
第三章:政治への挑戦
30歳を過ぎた頃、私は魯の国の政治に関わるようになりました。しかし、理想と現実のギャップに苦しみました。腐敗した官僚たちを目の当たりにし、どうすれば国を正しい方向に導けるのか、悩み続けました。
魯の国は、表面上は周王朝の礼制を守っているように見えました。しかし、実際には権力者たちの私利私欲が横行し、民の苦しみは日に日に増していました。
ある日、私は宰我という弟子と朝廷に向かう途中でした。道端で老人が泣いているのを見かけ、私たちは足を止めました。
「おじいさん、どうされましたか?」私が尋ねると、老人は涙ながらに答えました。
「私の息子が、重税に耐えられず逃げてしまったのです。残された家族は飢えに苦しんでいます」
この言葉を聞いた宰我が私に問いかけました。
「先生、なぜ政治家たちは民のことを考えないのでしょうか」
「宰我よ、それは彼らが本当の意味での教養を身につけていないからだ。知識だけでなく、徳も大切なのだ。為政者が徳を失えば、民は離れていく。これこそが国家衰退の始まりだ」
私たちは老人に食べ物を分け与え、さらに役所に掛け合って税の減免を求めました。この経験を通じて、私は政治の本質について深く考えさせられました。
政治に携わる中で、私は「徳治主義」という考えを形成していきました。為政者自身が高い徳を持ち、民の模範となることで、国全体を正しい方向に導くことができる。そう考えたのです。
しかし、この考えを実践することは容易ではありませんでした。権力者たちは自分の地位や利益を守ることに汲々としており、民のことを顧みる者はほとんどいませんでした。
ある日、朝廷での会議の後、私は失意のうちに家路につきました。そこで、かつての師である王叔と再会しました。
「孔丘、どうしたのだ?何か悩みがあるようだが」
私は溜息をつきながら答えました。
「王叔様、政治の現実があまりにも理想と乖離しています。どうすれば国を正しい方向に導けるのでしょうか」
王叔は優しく微笑んで言いました。
「孔丘よ、大きな変化は一朝一夕には起こら
ない。しかし、諦めてはいけない。お前のような志を持つ者が、少しずつ世の中を変えていくのだ。まずは、自分の周りから始めなさい」
この言葉に励まされ、私は教育の重要性を再認識しました。政治を直接変えることは難しくても、人々に正しい教えを広めることで、少しずつでも世の中を変えられるのではないか。そう考えた私は、私塾を開くことを決意しました。
「子路、子貢、顔回」私は最も信頼する弟子たちを呼び集めました。「私は塾を開こうと思う。身分や貧富の差に関係なく、学ぶ意欲のある者は誰でも受け入れたい」
弟子たちは喜んでこの提案に賛同しました。こうして、私の人生は新たな段階に入ったのです。
第四章:教育者としての道
35歳で私塾を開いた私のもとには、多くの若者が集まってきました。身分や貧富の差に関係なく、学ぶ意欲のある者は誰でも受け入れました。これは当時としては画期的なことでした。

私の教育方法は、一方的に知識を教え込むのではなく、対話を通じて弟子たちの思考を促すというものでした。
ある日の授業でのことです。私は弟子たちに問いかけました。
「君たちは、人として最も大切なものは何だと思うか?」
様々な答えが返ってきました。「知識です」「勇気です」「忠誠です」
そして、子貢が答えました。「先生、私は『仁』だと思います」
「なるほど、では子貢よ、『仁』とは具体的にどういうことだと思うか?」
子貢は少し考えてから答えました。「他者を思いやり、自分がされたくないことは人にもしないということではないでしょうか」
「良い答えだ。『仁』とは、まさにそういうことだ。しかし、それを実践することは容易ではない。日々の生活の中で、常に自分を省み、他者への思いやりを忘れないことが大切だ」
このような対話を通じて、弟子たちは単に知識を得るだけでなく、深く考える力を養っていきました。
私の教えの中心にあったのは、「仁」「礼」「義」「智」「信」という五つの徳目でした。
「仁」は他者への思いやり、「礼」は社会の秩序を保つための規範、「義」は正義と道徳、「智」は知恵、「信」は誠実さを意味します。これらの徳目を身につけることで、人は真の君子(理想的な人格者)になれると私は考えました。
ある日、弟子の子路が私に尋ねてきました。
「先生、どうすれば立派な人間になれますか?」
「子路よ、まず自分を磨くことだ。礼を知り、義を行い、仁を体現する。そうすれば、おのずと周りの人々も変わっていくだろう」
「しかし先生、それは難しいことではありませんか?」
「確かに難しい。だが、諦めてはいけない。日々の小さな行動の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらすのだ。今日より明日、明日より明後日と、少しずつでも成長し続けることが大切だ」
このような教えを通じて、弟子たちは単に知識を得るだけでなく、人格の形成にも努めました。
私の教育方法はまた、弟子たちの個性を重視するものでした。同じ質問でも、弟子によって異なる答えを与えることがありました。これは、それぞれの弟子の性格や能力に応じて、最適な教えを与えるためでした。
例えば、積極的で行動力のある子路には、
「学んだことは、すぐに実践しなさい。しかし、急ぎすぎてはいけない。熟慮してから行動することを忘れるな」
と諭しました。一方、慎重で思慮深い子貢には、
「考えすぎて行動が遅れることのないように。時には勇気を持って一歩を踏み出すことも大切だ」
と助言しました。
このような個別指導により、弟子たちはそれぞれの長所を伸ばし、短所を克服していきました。
教えながら、私自身も成長していきました。弟子たちとの対話を通じて、自分の考えを整理し、深めていったのです。時には鋭い質問を投げかけてくる弟子もおり、そのたびに私も新たな気づきを得ました。

「先生、『仁』を実践することと、国の法律を守ることが矛盾する場合はどうすればいいのでしょうか?」
ある日、弟子の冉有がそう質問してきました。これは、倫理と法の関係という難しい問題です。私はしばらく考えてから答えました。
「難しい質問だ、冉有。基本的には、国の法律を守ることも『礼』の一つだ。しかし、法律が明らかに『仁』に反する場合もあるだろう。そのような時は、自分の良心に従って行動することも必要かもしれない。ただし、その結果には責任を持たなければならない」
このような対話を重ねることで、私の思想はより深まり、体系化されていきました。そして、これらの教えは後に『論語』としてまとめられ、後世に伝えられることになるのです。
第五章:諸国遍歴の旅
50歳を過ぎた頃、私は魯の国を出て、諸国を巡る旅に出ました。理想の政治を実現するため、様々な国の君主に会いに行ったのです。この旅は14年もの長きにわたりました。
旅の始まりは、魯の国の政治への失望からでした。当時の魯の君主は、政治よりも遊興に耽っており、国の政策は大夫と呼ばれる貴族たちの思惑によって左右されていました。
「このままでは、魯の国は滅びてしまう」
私はそう考え、他国で自分の理想を実現しようと決意したのです。
最初に訪れたのは、衛の国でした。衛の霊公は、初めは私の話に興味を示しました。
「孔丘先生、あなたの『徳治』の考えは面白い。具体的にはどのようなことをすればいいのだろうか?」
「君主様、まずは自らが模範を示すことです。倹約に努め、民の苦しみを理解し、賢人を登用することが大切です」
しかし、霊公は私の助言を実践することはありませんでした。相変わらずの贅沢な暮らしを続け、側近の諂いに耳を傾けるばかりでした。
失意のうちに衛を後にした私は、次に宋の国を訪れました。しかし、ここでも理想の実現は困難でした。宋の君主は、私の教えを危険思想とみなしたのです。
「孔丘の教えは、既存の秩序を乱すものだ。国外に追放せよ」
幸い、弟子たちの機転により、私たちは難を逃れることができました。しかし、この経験は私に大きな衝撃を与えました。
「子路、私たちの教えは本当に正しいのだろうか?」
落胆する私に、子路は力強く答えました。
「先生、私たちの教えは正しいのです。それを理解できない者がいるだけです。諦めないでください」
弟子たちに励まされ、私たちは旅を続けました。陳、蔡、葉など、様々な国を訪れましたが、どこでも理想の実現は困難でした。時には命の危険にさらされることもありました。

ある時、楚の国との国境地帯で、私たちは食料が尽き、7日間も飢えに苦しみました。
「先生、もう諦めて魯に帰りましょう」弟子の子路が提案しました。
しかし、私は諦めませんでした。
「子路よ、諦めてはいけない。たとえ今は理解されなくても、いつかきっと私たちの教えは広まるはずだ。それまで、我々は学び続け、教え続けなければならない」
この旅の中で、私は多くのことを学びました。各国の政治制度、文化、習慣の違いを目の当たりにし、自分の思想をより普遍的なものに深めていったのです。
また、様々な人々との出会いも私の思想を豊かにしました。ある日、老子という思想家と出会い、深い議論を交わしました。

「孔丘よ、お前は人為的な徳や礼を説くが、それは自然の道に反するのではないか」
老子の問いかけに、私はこう答えました。
「確かに、過度に人為的なものは自然の道に反するかもしれません。しかし、人間社会には一定の秩序が必要です。重要なのは、自然の理に沿った形で徳や礼を実践することではないでしょうか」
このような対話を通じて、私の思想はさらに深まり、柔軟性を増していきました。
14年に及ぶ諸国遍歴の旅は、決して平坦なものではありませんでした。しかし、この経験を通じて、私の思想はより普遍的で深いものになったのです。そして、いつかはこの教えが世に広まり、理想の社会が実現することを、私は信じ続けました。
第六章:教えの集大成
60歳を過ぎた頃、私は魯の国に戻りました。諸国遍歴の旅で得た経験と知恵を胸に、再び教育活動に専念することにしたのです。
魯に戻った私を、多くの弟子たちが歓迎してくれました。彼らの中には、すでに各地で教えを広めている者もいました。
「先生、お帰りなさい。私たちは先生の教えを守り、実践してきました」
弟子の顔回がそう言って迎えてくれた時、私は深い感動を覚えました。自分の教えが、確実に次の世代に受け継がれていることを実感したのです。
この頃から、私はこれまでの教えを体系化し、より多くの人々に伝えることに力を注ぎました。弟子たちと共に、日々議論を重ね、教えの本質を明確にしていきました。
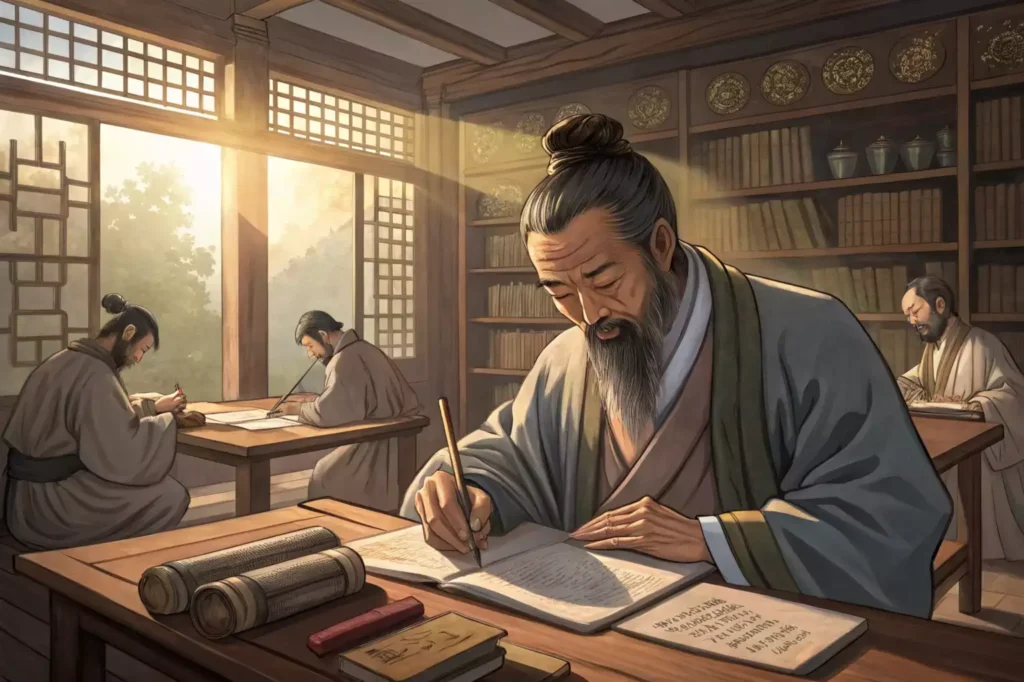
ある日、弟子の子貢が私に尋ねました。
「先生、あなたの教えはとても貴重です。これらをどのように後世に伝えればよいでしょうか?」
私はしばらく考えてから答えました。
「子貢よ、私の言葉そのものは重要ではない。大切なのは、その精神を理解し、実践することだ。君たち一人一人が、自分の言葉で私の教えを解釈し、伝えていってほしい」
この言葉を聞いた弟子たちは、それぞれの方法で私の教えを記録し、解釈を加えていきました。ある者は私の言動を詳細に記録し、またある者は教えの本質を自分なりにまとめていきました。
「先生、私たちはあなたの教えを必ず後世に伝えます」と顔回が誓いました。
「ありがとう、顔回。しかし、単に言葉を伝えるだけでは意味がない。その精神を理解し、実践することが大切だ。そして、時代に合わせて解釈し、適用していくことも必要だろう」
私は、自分の教えが弟子たちによって受け継がれ、やがて大きな思想の流れになっていくことを予感していました。しかし、それがどのような形で後世に伝わるかは、私にも分かりませんでした。
この時期、私は特に「仁」の概念を深めることに力を注ぎました。「仁」とは単なる思いやりではなく、人間関係の理想的なあり方を示す概念です。
「人間は一人では生きられない。互いに助け合い、支え合うことで初めて、真の人間になれるのだ」
私はよくこう弟子たちに語りかけました。そして、「仁」を実践するための具体的な方法として、「忠恕」の教えを説きました。
「忠」とは自分の心に誠実であること、「恕」とは他者への思いやりです。この二つを実践することで、人は「仁」に近づくことができるのです。
また、「礼」の重要性も強調しました。「礼」は単なる形式的な儀式ではなく、人間関係を調和させ、社会の秩序を保つための重要な要素です。
「礼を知らざれば以て立つ無し」(礼を知らなければ、人として立つ
ことはできない)
この言葉は、後に『論語』の中で最も有名な一節の一つとなります。
教えを集大成する中で、私は自分の思想の核心を「天」という概念に見出しました。「天」とは、単なる自然現象ではなく、宇宙の根源的な秩序を表す概念です。
「人間は天の意志に従って生きるべきだ。そうすることで、個人も社会も調和のとれた状態になる」
この考えは、後の中国思想に大きな影響を与えることになります。
しかし、教えを集大成する過程は決して平坦なものではありませんでした。時には弟子たちの間で解釈の違いによる議論が起こることもありました。
「先生、『正名』の概念をどのように理解すればよいでしょうか」
ある日、弟子の子路がそう尋ねてきました。「正名」とは、名実一致の重要性を説く概念です。
「子路よ、『正名』とは、物事の名称とその実態を一致させることだ。君主は君主らしく、臣下は臣下らしく、父は父らしく、子は子らしくあるべきだ。名と実が乖離すれば、社会は混乱する」
このような対話を通じて、私の思想はより明確になっていきました。そして、これらの教えは弟子たちによって記録され、後に『論語』として編纂されることになります。
私は、自分の教えが後世にどのように伝わるかを正確に予測することはできませんでした。しかし、人々が互いに思いやり、調和のとれた社会を築いていくという理想は、必ず受け継がれていくと信じていました。
「我々の教えは、決して一朝一夕に実現するものではない。しかし、諦めずに努力を続ければ、必ずや理想の社会は実現するだろう」
こう語りかけながら、私は弟子たちと共に、教えの集大成に励んだのです。
第七章:晩年の思い
70歳を過ぎた私は、もはや諸国を巡ることはできませんでした。しかし、多くの弟子たちが私のもとを訪れ、学びを続けていました。私の教えは、彼らを通じて少しずつ広がっていったのです。
ある日、最も信頼する弟子の一人である顔回が私を訪ねてきました。彼の表情は悲しみに満ちていました。
「先生、私はあなたの教えを広めようと努力していますが、なかなか人々に理解してもらえません。時には嘲笑されることさえあります。どうすればよいのでしょうか」
私は顔回の肩に手を置き、優しく語りかけました。

「顔回よ、諦めてはいけない。大切なのは、自分の信念を曲げないことだ。たとえ今は理解されなくても、正しいことを続ければ、いつかは必ず理解されるときが来る」
「しかし先生、それまでにどれほどの時間がかかるのでしょうか」
「それは分からない。しかし、我々にできるのは、今この瞬間に全力を尽くすことだけだ。未来のことは天に任せよう」
この会話の後、顔回は新たな決意を胸に、再び旅立っていきました。
晩年の私は、これまでの人生を振り返る時間も多くなりました。成功も失敗も、すべての経験が私を形作ってきたのだと感じています。
ある静かな夜、庭に座って月を眺めていると、孫の子思が私に寄り添いました。

「おじいさま、あなたの人生に後悔はありませんか?」
私は少し考えてから答えました。
「後悔? そうだな…もっと早くから学び始めていれば、もっと多くのことができたかもしれない。でも、人生そのものを後悔してはいない。私は自分の道を歩んできたのだから」
「おじいさまの教えは、きっと後世に伝わっていくと思います」
子思の言葉に、私は微笑みました。
「そうあってほしいものだ。しかし、大切なのは言葉そのものではない。その精神が受け継がれ、人々の心の中で生き続けることだ」
晩年の私は、自分の教えが単なる学問ではなく、人々の生き方そのものに影響を与えるものであってほしいと願っていました。
「学んだことを実践しなければ意味がない。知識は行動を通じて初めて真の知恵となるのだ」
私はよくこう弟子たちに語りかけました。
73歳の時、私は静かに目を閉じました。しかし、私の教えは弟子たちによって受け継がれ、後の世に大きな影響を与えることになりました。
エピローグ:孔子の遺産
私、孔子の人生は決して平坦なものではありませんでした。貧しさ、政治的な挫折、危険な旅…様々な困難がありました。しかし、学ぶことへの情熱と、世の中をよりよくしたいという思いは、決して消えることはありませんでした。
私の教えの核心は、「仁」という概念です。これは、人を思いやり、互いに助け合うことの大切さを説いたものです。また、「礼」を重んじ、社会の秩序を保つことの重要性も説きました。
「学而時習之、不亦説乎」(学びて時にこれを習う、亦た説しからずや)
これは『論語』の冒頭の言葉です。学ぶことの喜びを表現したこの言葉は、私の教育哲学の根幹を成すものです。知識を得ることだけでなく、それを実践し、自分のものとすることの大切さを説いたのです。
私の弟子たちは、これらの教えを各地に広めていきました。そして、私の死後何百年もの間、中国だけでなく東アジア全体に大きな影響を与え続けることになったのです。
私の教えは、単なる道徳的な規範ではありません。それは、人間としてどう生きるべきか、社会をどのように作り上げていくべきかという、根本的な問いに対する一つの答えなのです。
「己の欲せざる所を人に施すなかれ」
これは、私の教えの中でも最も有名な言葉の一つです。自分がされたくないことは他人にもするな、という簡単な言葉ですが、これを実践することで、人々は互いを思いやり、調和のとれた社会を築くことができるのです。
現代を生きる皆さんへ。私の時代とは多くのことが変わっているでしょう。技術は進歩し、社会の仕組みも大きく変化したことでしょう。しかし、人を思いやり、学び続けることの大切さは、きっと今でも変わらないはずです。
「学びて思わざれば則ち罔し、思いて学ばざれば則ち殆し」
この言葉の意味を考えてみてください。学ぶだけでなく、深く考えること。そして、考えるだけでなく、実際に学ぶこと。この両方が大切なのです。
皆さんも、自分の道を歩んでください。困難があっても諦めず、常に学び、成長し続けてください。そうすれば、きっと素晴らしい人生が待っているはずです。
そして、個人の幸福だけでなく、社会全体の調和を考えてください。一人一人が「仁」の心を持ち、互いを思いやることで、きっとより良い世界を作ることができるはずです。
私の教えが、皆さんの人生の指針の一つとなれば幸いです。しかし、盲目的に従うのではなく、自分で考え、実践することを忘れないでください。それこそが、真の学びなのですから。



































































































































