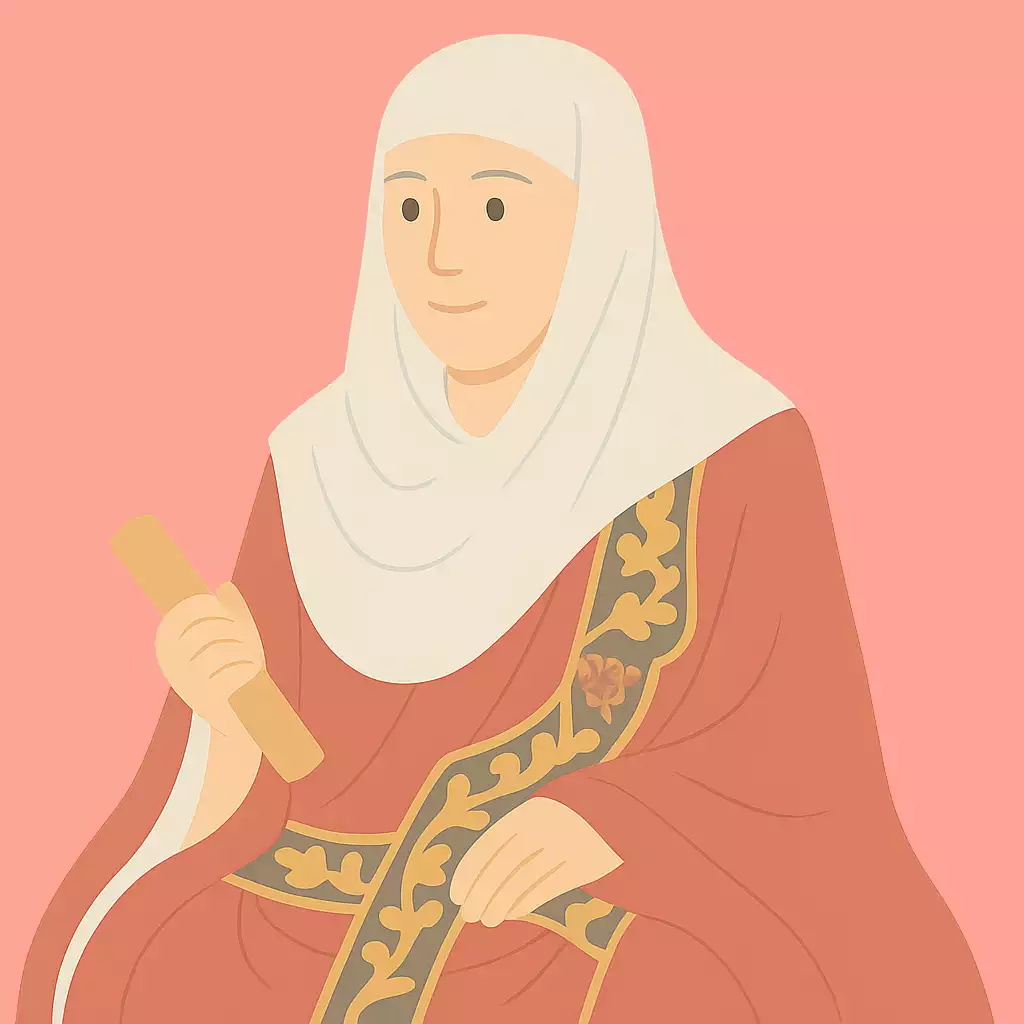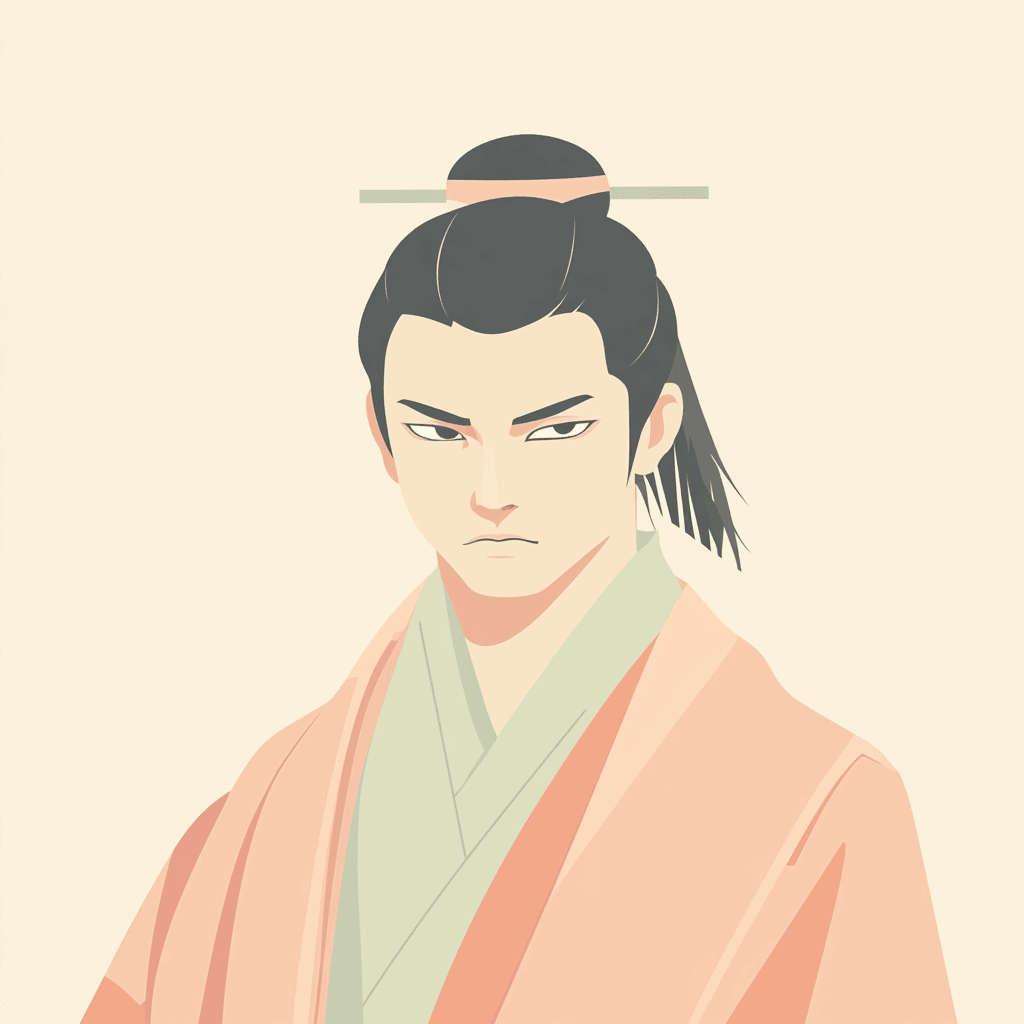第一章:幼少期の記憶
私の名は石川五右衛門。生まれは摂津国(今の大阪府)だ。幼い頃の記憶は曖昧だが、貧しい農家の子として育ったことは鮮明に覚えている。
我が家は小さな藁葺きの家で、冬になると隙間風が吹き込み、身を寄せ合って寒さをしのいだものだ。食事も質素で、麦飯に漬物、時々野菜の煮物が出る程度だった。しかし、そんな中でも、家族の絆だけは強かった。
父は厳しい人だった。「五右衛門、お前は強くならなければならない」と、よく言っていた。当時は意味が分からなかったが、今になって思えば、厳しい時代を生き抜くための教えだったのだろう。
ある日、父と一緒に田んぼで働いていた時のことだ。突然、父が私を呼び止めた。
「五右衛門、よく聞け」
父の真剣な表情に、私は緊張した。
「この世は強い者が弱い者を支配する。だが、本当の強さとは何か、分かるか?」
私は首を傾げた。父は続けた。
「本当の強さとは、弱い者を守る力だ。覚えておけ」
その言葉は、後の私の人生に大きな影響を与えることになる。
母は優しかった。夜な夜な私を抱きしめ、「五右衛門、お前は特別な子だ」と囁いていた。その言葉が、後の私の人生を大きく変えることになるとは、誰も想像していなかっただろう。
ある夜、母と二人きりになった時、私は尋ねた。
「母上、私が特別だというのは、どういう意味ですか?」
母は優しく微笑んだ。
「五右衛門、お前には人の心を動かす力がある。それは、この世で最も大切な力だ」
当時の私には、その言葉の意味が分からなかった。しかし、母の言葉は私の心に深く刻まれ、後々まで私を支え続けることになる。
幼い頃の私には、もう一つ忘れられない思い出がある。それは、村の祭りの日のことだ。
五穀豊穣を祈る祭りで、村中が賑わっていた。屋台が立ち並び、太鼓の音が鳴り響く中、私は両親と一緒に歩いていた。
突然、悲鳴が聞こえた。振り返ると、一人の老婆が倒れていたのだ。周りの人々は驚いて立ち止まったが、誰も動こうとしない。
その時、私は咄嗟に老婆に駆け寄っていた。
「大丈夫ですか?」
老婆は苦しそうに息をしていた。私は周りの人々に叫んだ。
「誰か、助けて!」
その声に、ようやく村人たちが動き出した。老婆は無事に介抱され、大事には至らなかった。
その夜、父は珍しく私を褒めた。
「よくやった、五右衛門。人を助けることを恐れるな」
この出来事は、私の中に「人を助けたい」という強い思いを芽生えさせた。それが後の私の行動の原動力となっていくのだ。
第二章:忍術との出会い
10歳の時、私の人生は大きく変わった。ある夜、見知らぬ男が我が家を訪れたのだ。
その日は、珍しく雨が降っていた。夕食を終えた頃、突然の来客に家族全員が驚いた。
「この子を預かりたい」
その男の名は服部半蔵。後に知ることになるが、彼は伊賀忍者の頭領だった。
半蔵の姿は、今でも鮮明に覚えている。背は高くはなかったが、その眼光は鋭く、私の心の奥底まで見透かされているような気がした。
父は迷った様子だった。「なぜ、うちの子を?」
半蔵は静かに答えた。「この子には才能がある。私が育てれば、きっと大成する」
母は涙を浮かべながら頷いた。「五右衛門、行きなさい。これがお前の運命だ」
私は混乱していた。「でも、母上、父上…」
しかし、両親の決意は固かった。母は私を強く抱きしめ、こう囁いた。
「五右衛門、どんな時も、自分の心に正直に生きるのよ」
そう言って、母は私を半蔵に託した。
伊賀の山奥にある忍者の里で、私の修行が始まった。最初の数日間、私は家族との別れを悲しみ、眠れない夜を過ごした。しかし、やがて忍術の世界に魅了されていった。
剣術、忍術、毒薬の調合、変装の技。すべてが新鮮で、私は夢中になって学んだ。
特に印象に残っているのは、「心眼の術」だ。目を閉じ、周囲の気配を感じ取る技術だ。
「五右衛門、目に見えるものだけが真実ではない」
半蔵はそう言って、私に目隠しをさせた。
「さあ、私の動きを感じ取れ」
最初は全く分からなかったが、日々の訓練で少しずつ上達していった。ある日、ついに半蔵の動きを完全に読み取ることができた。
「よくやった、五右衛門」
半蔵の口調は普段と変わらなかったが、その目には確かに喜びの色があった。
半蔵は厳しい師匠だった。「五右衛門、お前には才能がある。だが、才能だけでは生き残れん」
その言葉を胸に、私は必死に修行に励んだ。時には厳しい罰もあった。一度、任務に失敗した時は、丸一日食事を抜かれたこともある。
しかし、そんな中でも、半蔵は時折優しさを見せた。ある日、私が高熱で寝込んだ時、半蔵は一晩中私の側で看病してくれたのだ。
「師匠、なぜそこまで…」
半蔵は静かに答えた。「お前は単なる弟子ではない。私の息子同然だ」
その言葉に、私は胸が熱くなった。
修行の日々は厳しかったが、同時に充実していた。特に、同じ頃に入門してきた風魔小太郎とは、良きライバルであり、親友となった。
「五右衛門、今度の試験は負けないぞ」
小太郎はいつもそう言って、私を競争に誘った。その度に、私たちは切磋琢磨し、互いに成長していった。
しかし、修行が進むにつれ、私の心に疑問が芽生え始めていた。なぜ、私たちは影に潜まなければならないのか。なぜ、力ある者たちに仕えなければならないのか。
その疑問が、やがて私の運命を大きく変えることになるのだ。
第三章:盗賊への道
15歳の時、私は一人前の忍者として認められた。しかし、その頃から、私の心に疑問が芽生え始めていた。
「なぜ、私たちは影に潜まなければならないのか」
「なぜ、力ある者たちに仕えなければならないのか」
そんな疑問を半蔵にぶつけると、彼は悲しそうな顔をした。
「五右衛門、世の中はそう単純ではない。我々には守るべきものがあるのだ」
半蔵の言葉に、私は反論した。
「でも、師匠。私たちの力を使えば、もっと多くの人々を助けられるはずです」
半蔵は深いため息をついた。
「五右衛門、お前の気持ちは分かる。だが、世の中を変えるのは、そう簡単ではないのだ」
その夜、私は眠れなかった。心の中で、半蔵の言葉と自分の思いが激しくぶつかり合っていた。
翌日、私は小太郎に相談した。
「小太郎、お前はどう思う?私たちの力を、もっと世のために使えないものか」
小太郎は真剣な表情で答えた。
「五右衛門、お前の考えは間違っていない。だが、それを実行するのは危険だ」
私は決意した。「小太郎、私は行く。この里を出て、自分の道を見つける」
小太郎は驚いた様子だったが、すぐに理解を示してくれた。
「分かった。だが、気をつけろよ。外の世界は厳しいぞ」
その夜、私は里を抜け出した。半蔵への感謝の気持ちと、申し訳ない気持ちが胸に去来した。だが、自分の信念を貫くためには、この道しかないと信じていた。
自由を求めて放浪の旅に出た私は、やがて盗賊の道を選んだ。しかし、私は普通の盗賊とは違った。金持ちから盗んで貧しい者に与える。そんな義賊として名を馳せていったのだ。
最初の「仕事」は、今でも鮮明に覚えている。ある豪商の屋敷に忍び込み、金品を盗み出したのだ。
その夜、私は盗んだ金を持って、貧しい農民の家々を回った。
「これを使ってください」
そっと置いていった金を見つけた農民たちの驚きと喜びの表情。それは、私の心に深く刻まれた。
「これだ。これが私のやるべきことなんだ」
その日から、私の義賊としての活動が本格的に始まった。
しかし、その道は決して平坦ではなかった。ある時は、盗みの最中に見つかり、九死に一生を得たこともある。
「くそっ、もう少しで…」
屋敷の塀を飛び越えながら、私は自分の未熟さを痛感した。
また、盗んだ金を分配する際にも、様々な問題に直面した。本当に困っている人を見分けるのは、思った以上に難しかったのだ。
「五右衛門様、私にも分けてください」
そう懇願する人々の中には、本当に困窮している人もいれば、単に欲深い者もいた。その見極めに、私は苦心した。
そんな中、私は一人の老婆と出会った。彼女は、私が金を分け与えようとしても、頑なに受け取ろうとしなかった。
「わしはこれで十分じゃ。その金は、もっと困っている人に使ってくれ」
その老婆の言葉に、私は深く感銘を受けた。そして、自分の行動の意味を、改めて考えさせられたのだ。
「金を配るだけでは、本当の助けにはならない。人々の心を変えていく必要がある」
その気づきが、後の私の行動に大きな影響を与えることになる。
第四章:豊臣秀吉との対立
20歳を過ぎた頃、私の名は全国に知れ渡っていた。「石川五右衛門」の名は、貧しい者たちの希望の象徴となっていた。
ある村での出来事は、今でも鮮明に覚えている。干ばつで苦しむ村人たちを助けるため、近くの豪商から米を盗み出したのだ。
「五右衛門様、ありがとうございます!」
涙を流して喜ぶ村人たちを見て、私は自分の行動に確信を持った。
しかし、それは同時に権力者たちの目に留まることも意味していた。特に、天下統一を目指す豊臣秀吉にとって、私の存在は目障りだったようだ。
ある日、秀吉の家臣である前田利家が私のもとを訪れた。その日、私は山中の隠れ家にいた。
突然、見知らぬ武士の一団が現れ、私は身構えた。しかし、その中の一人が手を上げ、こう言った。
「待て、石川五右衛門。我々は敵ではない」
その男こそが、前田利家だった。
利家は続けた。「五右衛門、秀吉様が御意見したいそうだ」
私は警戒した。「何の用だ?」
利家は苦笑いを浮かべた。「お前の力を認めておられる。秀吉様の下で働かないか?」
その提案に、私は驚いた。天下人・秀吉からの誘いだ。普通なら、二つ返事で承諾するところだろう。
しかし、私は断った。「誰かの下で働くつもりはない。この国を変えるのは、この石川五右衛門だ」
利家は残念そうな顔をした。「そうか。だが、気をつけろ。秀吉様は手ぬるい方ではないぞ」
その言葉通り、秀吉の追っ手が私を追い始めた。しかし、忍術の技を持つ私を捕まえるのは容易ではなかった。
ある時は、町の真ん中で追っ手に囲まれたこともあった。
「観念しろ、石川五右衛門!」
追っ手たちが刀を抜く中、私は冷静に状況を分析した。そして、瞬時に行動に移った。
「変化の術!」
煙幕を張り、私は老人に変装して逃げ出した。追っ手たちが混乱する中、私はそっと町を抜け出したのだ。
また、ある時は山中で追い詰められたこともある。崖っぷちに立たされ、もう逃げ場はないように見えた。
「ここまでか…」
そう思った瞬間、私は父の言葉を思い出した。
「本当の強さとは、弱い者を守る力だ」
その言葉に勇気づけられ、私は決死の覚悟で崖を飛び降りた。奇跡的に生き延び、再び逃げおおせたのだ。
そんな逃亡生活の中で、私は多くの人々と出会い、その度に自分の信念を強めていった。
貧しい農民、虐げられた商人、希望を失った若者たち。彼らの苦しみを目の当たりにするたびに、私は思った。
「この国は、変わらなければならない」
そして、その変革の先頭に立つのは、この石川五右衛門だと。
第五章:伝説の始まり
追っ手をかわしながら、私は各地を転々とした。その過程で、多くの仲間たちと出会った。
中でも、風魔小太郎という忍者は私の良き友となった。彼もまた、既存の忍者の在り方に疑問を持っていたのだ。
ある夜、小太郎と酒を酌み交わしながら、私たちは語り合った。
「五右衛門、お前の考えは正しい。だが、一人では何も変えられん」
小太郎の言葉に、私は考えさせられた。確かに、これまで私は孤独な戦いを続けてきた。しかし、本当に国を変えるためには、もっと大きな力が必要だ。
「小太郎、お前の言う通りだ。仲間を集めよう」
その夜、私たちは新たな計画を立て始めた。
我々は、単なる盗賊団ではない。民衆の味方として、この国を変える存在になろうと決意したのだ。
まず、我々は情報網を築いた。各地に協力者を置き、困っている人々の情報を集めた。そして、その情報を基に、的確な「救済活動」を行った。
ある時は、重税に苦しむ村を救うため、代官所から年貢米を奪い返した。また、ある時は、悪徳商人から騙し取られた金を取り戻し、村人たちに返還した。
そんな活動を続けるうちに、我々の仲間は増えていった。元忍者、浪人、農民、商人…様々な背景を持つ人々が、我々の理念に共鳴して集まってきたのだ。
ある日、小太郎が興奮した様子で私のもとにやってきた。
「五右衛門、聞いてくれ!我々の噂が、都にまで広まっているそうだ」
私は驚いた。「本当か?」
小太郎は頷いた。「ああ。『義賊・石川五右衛門』として、民衆の間で語り継がれているらしい」
その話を聞いて、私は複雑な思いに駆られた。嬉しさと同時に、責任の重さも感じたのだ。
「小太郎、我々の戦いは、これからが本番だ」
私たちは、さらなる高みを目指して活動を続けた。しかし、その過程で、新たな課題にも直面した。
例えば、我々の活動を真似た偽物の集団が現れ始めたのだ。彼らは我々の名を騙り、単なる強盗行為を働いていた。
「くそっ、こんなことでは、民衆の信頼を失ってしまう」
我々は、そういった偽物たちの取り締まりにも力を注いだ。時には、彼らと直接対決することもあった。
また、我々の活動が大きくなるにつれ、内部での意見の相違も生じ始めた。
「もっと過激な行動を取るべきだ」
「いや、あくまで平和的な方法で」
そんな議論が、度々起こるようになった。
その度に、私は仲間たちに語りかけた。
「我々の目的は、この国を良くすることだ。そのためには、時に力が必要かもしれない。しかし、決して民衆を傷つけてはならない」
そうして、我々は少しずつ、しかし着実に、その影響力を広げていった。
そして、ついに我々は、最大の挑戦に向けて動き出す。それは、豊臣政権の中枢、大坂城に潜入し、秀吉の金蔵を襲うという、前代未聞の計画だった。
第六章:大返しの計画
25歳の時、我々は大胆な計画を立てた。京の都に潜入し、秀吉の金蔵を襲うのだ。
この計画には、二つの目的があった。一つは、秀吉の財力を削ぎ、民衆への圧政を弱めること。もう一つは、その金を使って、全国の貧しい人々を救済することだ。
計画の詳細を詰める中で、小太郎が不安そうな表情を浮かべた。
「五右衛門、無謀すぎるぞ」
私も、この計画の危険性は十分に理解していた。しかし、それでも実行する価値はあると信じていた。
「小太郎、分かっている。だが、この金で、貧しい者たちを救うんだ」
私たちは、慎重に準備を進めた。まず、大坂城の詳細な情報を集めることから始めた。城内の見取り図、警備の配置、交代のタイミングなど、あらゆる情報を収集した。
その過程で、思わぬ協力者も現れた。大坂城で働く下級武士の一人が、我々の活動に共鳴し、内部情報を提供してくれたのだ。
「五右衛門殿、この情報が役立つことを願っています」
その武士の勇気に、私は深く感謝した。
準備が整うまでに、約半年の時間がかかった。その間、我々は何度も計画を練り直し、あらゆる状況を想定して対策を立てた。
そして、ついに計画実行の日が来た。
その日、我々は五つの小隊に分かれて行動することにした。私と小太郎を含む主力部隊が金蔵に向かい、他の隊は囮として、城内の別の場所で騒ぎを起こす役目だ。
夜陰に紛れて、我々は城内に潜入した。忍術を駆使して、警備の目をかいくぐる。
「行くぞ」
私の合図で、各隊が一斉に動き出した。
予定通り、城内の各所で騒ぎが起こり始めた。警備の注意が分散する中、我々主力部隊は金蔵へと向かった。
そして、ついに金蔵の前にたどり着いた。
「よし、開けるぞ」
しかし、扉を開けた瞬間、予想外の展開が待っていた。
金蔵の中で、秀吉が一人で座っていたのだ。
「よく来たな、石川五右衛門」
私は驚いた。「なぜ、ここに?」
秀吉は静かに答えた。「お前の考えを聞きたかったからだ」
その瞬間、私は全てを悟った。我々の計画は、最初から秀吉に読まれていたのだ。
第七章:秀吉との対話
金蔵の中で、私と秀吉は長い時間、話し合った。
秀吉は、意外にも穏やかな口調で語り始めた。
「五右衛門、お前の活動は知っている。民を救おうとする志は立派だ」
私は警戒しながらも、秀吉の言葉に耳を傾けた。
秀吉は続けた。「だが、盗みでは何も変わらん。本当に国を変えたいのなら、もっと大きな力が必要だ」
私は反論した。「では、どうすれば?秀吉殿、あなたには力がある。なぜ、民のために使わないのですか?」
秀吉は深いため息をついた。
「簡単ではないのだ。この国を統一し、平和を保つには、時に厳しい決断も必要になる」
秀吉の言葉に、私は複雑な思いを抱いた。確かに、国を治めることの難しさは理解できる。しかし、それでも…
「でも、民衆の苦しみを見過ごすことはできません」
秀吉は静かに頷いた。
「分かっている。だからこそ、お前の力が必要なのだ」
そう言って、秀吉は驚くべき提案をした。
「五右衛門、共に国を作ろう。お前の力を貸してくれ」
その言葉に、私は大きな衝撃を受けた。天下人・秀吉からの直接の誘いだ。これは、国を変える大きなチャンスかもしれない。
しかし、同時に迷いもあった。秀吉の下で働くことで、本当に民衆を救えるのか。それとも、結局は権力者の手先になってしまうのか。
私は深く考え込んだ。そして、ついに決断を下した。
「すまない、秀吉殿。だが、私には私の道がある」
秀吉は悲しそうな顔をした。「そうか。ならば、仕方がない」
その瞬間、金蔵の扉が開き、多くの兵士たちが押し寄せてきた。
「石川五右衛門、お前を捕縛する」
私は観念した。しかし、小太郎たちは何とか逃げ出すことができた。
「五右衛門!」
小太郎の叫び声が聞こえたが、私は首を振った。
「行け、小太郎。我々の志を忘れるな」
そう言って、私は兵士たちに身を委ねた。
秀吉は最後にこう言った。
「五右衛門、お前との対話は有意義だった。この国の未来について、改めて考えさせられたよ」
その言葉に、私は小さな希望を感じた。たとえ自分は捕まったとしても、何かが変わるかもしれない。そう思うと、不思議と心が落ち着いた。
そして、私は静かに兵士たちに連れられていった。これが、石川五右衛門としての最後の姿となるのだろうか。
第八章:捕縛と処刑
牢に入れられた私は、自分の人生を振り返った。果たして、自分のしてきたことは正しかったのか。
暗い牢の中で、私は日々を過ごした。しかし、不思議なことに、絶望感はなかった。むしろ、これまでの自分の行動を冷静に見つめ直す機会となった。
ある日、牢番が私に話しかけてきた。
「五右衛門、お前の噂は本当だった。お前が助けた村の者たちが、嘆願書を出してくれたぞ」
その言葉に、私は胸が熱くなった。自分の行動が、確かに人々の心に届いていたのだ。
しかし同時に、新たな苦悩も生まれた。自分の行動が、思わぬ形で人々に影響を与えていたことに気づいたのだ。
「もし、私の行動が、かえって人々を危険に晒すことになっていたら…」
そんな思いが、私の心を苛んだ。
処刑の日が近づくにつれ、私は自分の信念と向き合った。そして、最後にたどり着いた結論。
「たとえ死んでも、私の志は生き続ける」
処刑の日、私は釜茹での刑に処された。しかし、最後の瞬間まで、私は諦めなかった。
処刑台に立たされた時、群衆の中に見覚えのある顔を見つけた。小太郎だ。彼は悲しそうな顔をしていたが、私は小さく頷いてみせた。
「さあ、最後の言葉はあるか?」と役人に問われ、私はこう答えた。
「天下の茶釜と言えども、釜は釜、人は人。されど、この茶釜、少し熱いぞ」
その言葉が、後世まで語り継がれることになるとは、その時の私には想像もつかなかった。
釜に入れられる直前、私は空を見上げた。青い空、白い雲。自由を象徴するようなその景色に、私は最後の別れを告げた。
そして、熱湯の中に沈みながら、私は思った。
「これで終わりではない。私の志は、必ず誰かに引き継がれる」
その思いと共に、私の意識は闇に包まれていった。
第九章:伝説の誕生
私の死後、思いもよらぬことが起こった。民衆の間で、私の物語が語り継がれ始めたのだ。
「石川五右衛門は死んでいない」
「五右衛門は今も貧しい者たちを助けている」
そんな噂が広まり、私の名は伝説となっていった。
処刑から数日後、小太郎たちは秘密裏に集まった。
「五右衛門の志を、俺たちが引き継ぐんだ」
小太郎の言葉に、仲間たちは強く頷いた。
彼らは、私の意志を継いで活動を続けた。しかし、以前とは少し違ったアプローチを取ることにした。
「暴力や盗みではなく、もっと建設的な方法で人々を助けよう」
そう決意し、彼らは各地で様々な活動を始めた。
貧しい村に井戸を掘る。孤児たちのための学校を建てる。不当な年貢に苦しむ農民たちのために、領主と交渉する。
そんな地道な活動が、少しずつ実を結んでいった。
ある日、小太郎たちが活動していた村で、思わぬ出来事が起こった。その村を訪れた旅の僧侶が、村人たちの話を聞いて驚いたのだ。
「石川五右衛門の仲間たちが、この村を助けてくれたと?」
僧侶は、その話を各地で語って回った。そして、その話は次第に広まっていった。
「石川五右衛門の魂は生きている」
「五右衛門の仲間たちが、今も人々を助けている」
そんな噂が、瞬く間に全国に広まった。
その噂は、やがて権力者たちの耳にも入った。中には、その活動を弾圧しようとする者もいた。
しかし、ある老臣が進言した。
「五右衛門たちの活動は、民の不満を和らげています。むしろ、我々にとっても有益なのではないでしょうか」
その言葉に、多くの領主たちが考えを改めた。
そして、驚くべきことに、中には積極的に彼らの活動を支援する領主も現れ始めたのだ。
「五右衛門の志は正しかった。我々も、民のために尽くさねばならない」
そんな変化が、少しずつ社会を変えていった。
小太郎たちの活動は、やがて大きな運動へと発展していった。各地に「五右衛門の会」が作られ、貧しい者たちを助ける活動が広まっていったのだ。
そして、その動きは単なる慈善活動にとどまらず、社会制度そのものを変える力となっていった。
不当な年貢の見直し、農民の権利保護、教育の機会均等…。少しずつではあるが、確実に社会は変わり始めたのだ。
私の魂は、きっと喜んでいただろう。
自分の死が、むしろ大きな変革の契機となったのだから。
第十章:未来への希望
時は流れ、世の中は大きく変わった。しかし、私の物語は今も語り継がれている。
江戸時代、明治時代、そして現代。時代が変わっても、「石川五右衛門」の名は人々の記憶に残り続けた。
私は、この世界がどうなったのか、天国から見守っている。まだまだ問題は多いが、少しずつ良い方向に向かっているようだ。
現代の日本。かつての封建制度は崩れ、民主主義が根付いている。人々は自由に意見を言い、選挙で代表者を選ぶことができる。
教育の機会も広がった。貧富の差に関わらず、多くの子どもたちが学校に通える。これは、私たちの時代では想像もできなかったことだ。
しかし、新たな問題も生まれている。格差の問題、環境破壊、国際紛争…。世の中が進歩しても、解決すべき課題は尽きないようだ。
そんな中、私は嬉しいことを目にした。
現代にも、私のような志を持つ人々がいるのだ。
社会起業家として貧困問題に取り組む若者。環境保護のために奔走する活動家。平和のために国境を越えて活動する人々。
彼らの姿を見ていると、私の魂が喜ぶのを感じる。
そして、私は信じている。これからも、私のような志を持つ者が現れ、世の中を良くしていくことを。
たとえ、一人の力は小さくても、その思いが次の世代に引き継がれていけば、必ず大きな変化を生み出せる。
私の物語が、そんな人々の勇気となることを願って。
最後に、未来を生きる人々へのメッセージを残したい。
「自分の信じる道を歩め。たとえ、その道が険しくとも」
「弱き者の味方となれ。そこにこそ、真の強さがある」
「諦めるな。お前たちの行動が、必ず世界を変える」
石川五右衛門の物語は、ここで幕を閉じる。しかし、その精神は、永遠に生き続けるだろう。
そして、いつの日か、本当に平等で公正な社会が実現することを、私は信じている。
その日まで、私は天国から見守り続けよう。