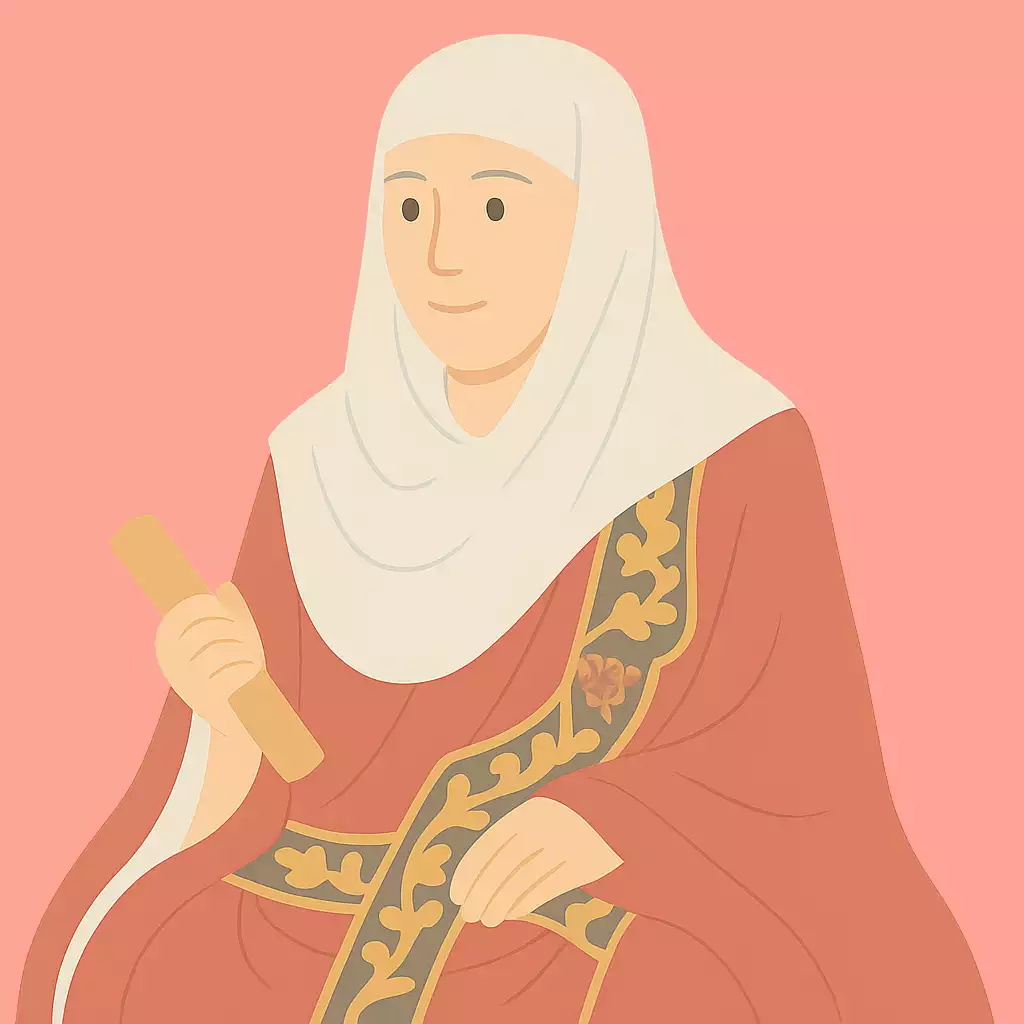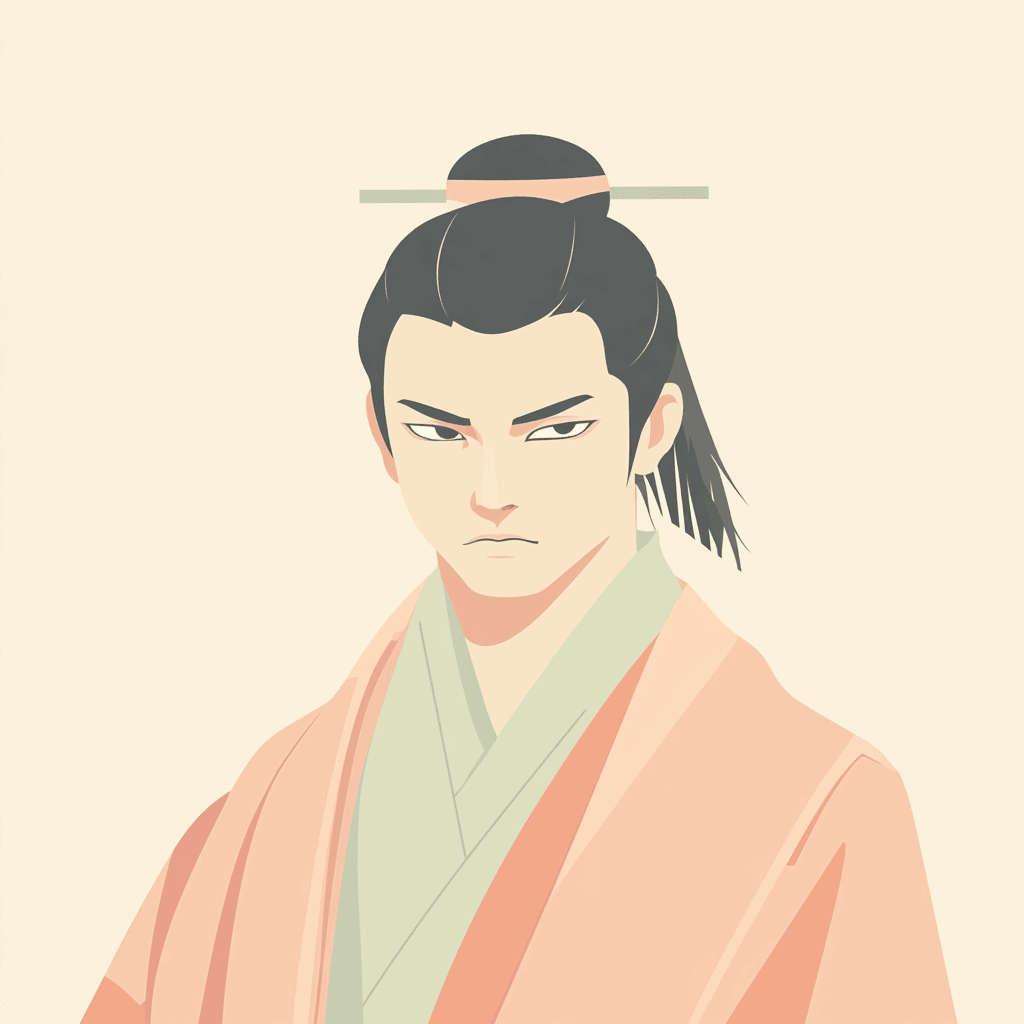第一章 – 若き日の野望
俺の名は織田信長。後の世に「第六天魔王」と呼ばれることになる男だ。だが、今はまだ若き日の織田家の跡取り息子に過ぎない。
生まれたのは尾張国勝幡城。父は織田信秀、母はつやの方だ。幼い頃から、俺は周りの子供たちとは違っていた。他の子が外で遊んでいる時、俺は城の中で歴史書を読みふけっていた。

「信長様、またそんな難しい本を読んでおられるのですか?」
俺の世話をしている侍女の於菊が、心配そうに声をかけてきた。
「ああ、於菊。この本を読めば読むほど、この国の未来が見えてくるんだ。」
「まあ、そんな難しいことを。でも、たまには外で遊んだ方がいいと思いますよ。」
於菊の言葉に、俺は首を振った。外で遊ぶ時間があれば、もっと多くのことを学びたかったのだ。
父・信秀はそんな俺を心配そうに見ていた。ある日、父が俺を呼び出した。
「信長、お前はいつも本ばかり読んでおるな。たまには外で遊んでこい。武芸の稽古もしっかりせねばならんぞ。」
父の言葉に、俺は反論した。
「いいえ、父上。この本を読めば読むほど、この国の未来が見えてくるのです。武芸も大切ですが、知恵がなければ天下は取れません。」
父は苦笑いを浮かべたが、それ以上は何も言わなかった。そんな父を俺は尊敬していた。厳しくも優しい父だった。しかし、周りの人々は俺のことを理解してくれなかった。
「あれが織田家の跡取り息子か?ふざけた格好をして、何をしているんだ。」
「織田大猿」と呼ばれ、笑いものにされることも多かった。長い髪を切り、派手な服を着て、型破りな行動をとる俺を、多くの人は理解できなかったのだ。
だが、俺には夢があった。いつか自分の手で天下を統一するという夢だ。そのためには、古い慣習にとらわれてはいられない。新しい時代には、新しい考え方が必要なのだ。
十歳を過ぎた頃、俺は初めて合戦の様子を目にした。父に連れられて城の天守閣から戦場を見下ろしたのだ。刀と刀がぶつかり合う音、兵士たちの雄叫び、そして血の匂い。その光景は俺の心に深く刻み込まれた。
「信長、よく見ておけ。これが戦だ。お前もいつかはこの立場に立つことになるぞ。」
父の言葉に、俺は固く頷いた。その時、俺の中で何かが変わった。本の中の世界だけでなく、現実の世界でも力を持ちたいと強く思うようになったのだ。
「父上、いつか私も戦に出陣させてください。」
「まだ早いぞ、信長。だが、その時が来たら、お前の力を見せてくれ。」
その日から、俺は武芸の稽古にも励むようになった。本で得た知識と、実際の戦いの技術。その両方を兼ね備えてこそ、真の戦国大名になれると信じたからだ。
第二章 – 家督相続と権力基盤の確立
時は流れ、俺は二十歳になっていた。父・信秀の死後、織田家の家督を相続することになったのだ。だが、それは決して平坦な道のりではなかった。
父の葬儀の日、俺は周囲の反対を押し切って、派手な服装で参列した。香を投げつけ、仏壇を蹴飛ばす。周りの人々は驚愕し、怒りの声を上げた。

「なんということだ!織田家の跡取りがこんな無礼な…」
「信秀殿も天国で嘆いておられるだろう。」
だが、俺には考えがあった。古い慣習にとらわれていては、新しい時代は切り開けない。変化を恐れる者たちに、俺は挑戦状を叩きつけたのだ。
「殿、家臣たちの中には、あなたの弟・信行を推す声もございます。」
側近の森可成が耳打ちしてきた。俺は冷ややかな笑みを浮かべた。
「そうか。ならば、奴らに俺の力を見せつけてやろうではないか。」
俺は家臣たちを集めて、自らの覚悟を示すことにした。清洲城の広間に集まった家臣たちの前で、俺は立ち上がった。
「諸君、聞いてくれ。織田家の未来は、俺が託されたのだ。誰がなんと言おうと、この俺が織田家を導く。ついてこられる者だけでいい。そうでない者は、今すぐに去れ!」
俺の言葉に、家臣たちはざわめいた。しかし、誰一人として立ち去る者はいなかった。その瞬間、俺は確信した。これらの者たちと共に、天下統一への道を歩めると。
家督を相続した俺は、まず尾張国内の統一に乗り出した。叔父の信康や弟の信行との争いは避けられなかった。
「兄上、なぜそこまでして権力にこだわるのです?」
信行が俺に問いかけてきた。
「信行、分かっているだろう。この国を変えるためには、強大な力が必要なのだ。俺にはその覚悟がある。お前にはないのか?」
結局、信行は俺に従うことを選んだ。だが、その選択が彼の運命を大きく変えることになるとは、その時は誰も予想していなかった。
尾張国内の統一が進む中、俺は新しい統治方法を次々と導入していった。
楽市楽座の制度を設け、商人たちの活動を自由にした。
「殿、そんなことをすれば、秩序が乱れてしまいます。」
家老の林秀貞が反対の声を上げた。
「秀貞、古い考えは捨てろ。商人たちの力を借りてこそ、国は豊かになるのだ。」
また、キリスト教の布教も許可した。当時の日本では珍しい決断だった。
「イエズス会のルイス・フロイス神父をお通しします。」
「よく来たな、フロイス神父。わが国の文化について、色々と教えてくれ。」

俺は西洋の文化や技術に強い関心を持っていた。鉄砲や航海術など、日本の発展に役立つものを積極的に取り入れようとしたのだ。
しかし、家督相続は始まりに過ぎなかった。隣国の今川義元が、大軍を率いて攻めてくるという知らせが届いたのだ。
「殿、今川軍の数は二万五千。我らはわずか二千五百です。逃げるしかありません!」
家臣の進言に、俺は首を振った。
「逃げるだと?ふざけるな。ここで勝てば、天下統一への第一歩となる。俺についてこい!」
俺の決断に、多くの家臣は驚いた。しかし、俺の目に迷いはなかった。これが天下統一への第一歩になると、俺は確信していたのだ。
第三章 – 桶狭間の戦いと天下統一への道
1560年5月19日、運命の日が訪れた。今川義元率いる大軍と、俺たち織田軍のわずかな兵力が激突する日だ。場所は桶狭間。狭い谷間で、敵の数の優位性を打ち消せると踏んだのだ。
前日の夜、俺は家臣たちを集めて最後の作戦会議を開いた。
「明日の戦、勝算はあるのか?」
家老の林秀貞が不安そうに尋ねた。
「ああ、必ず勝つ。」俺は自信を持って答えた。「奴らの大軍は、逆に足かせになる。狭い谷間では、数の利は生きない。」
作戦は単純だった。少数精鋭の部隊で義元の本陣を急襲する。義元さえ倒せば、敵軍は総崩れになるはずだ。
「しかし、殿。それでも敵の数は我らの10倍です。無謀ではないでしょうか。」
「臆病者は城に残っていろ。俺についてこれる者だけでいい。」
翌朝、雨が降り始めた。俺は空を見上げ、微笑んだ。
「天も味方してくれているようだな。」

突如、雷鳴が轟いた。その瞬間を狙って、俺は突撃の号令をかけた。
「いくぞ!織田軍、総攻撃!」
混乱する敵陣に、俺たちは猛烈な勢いで突っ込んでいった。刀を振るい、敵を倒していく。その中で、俺は今川義元の陣を目指した。
「義元!勝負だ!」
俺の声に、義元は驚いた顔を向けた。しかし、それが彼の最後の表情となった。俺の家臣が、義元の首を刎ねたのだ。

「殿!義元の首を上げました!」
家臣の声に、戦場は沸き立った。今川軍は総崩れとなり、俺たちの勝利が確定した。
戦いの後、俺は義元の首を前に深く考え込んだ。
「義元よ、お前は強大な軍勢を持ちながら、なぜ負けたのだ。」
答えは明白だった。義元は古い戦い方にとらわれすぎていた。時代は変わっている。新しい戦法、新しい考え方が必要なのだ。
桶狭間の戦いの勝利は、俺の名を一気に天下に轟かせた。これを機に、俺の天下統一への道は加速していった。
美濃を平定し、近江を手に入れ、そして畿内にも進出。かつての同盟者だった武田信玄や上杉謙信とも戦いを交えた。時に勝ち、時に苦戦しながらも、俺は着実に勢力を拡大していった。
長篠の戦いでは、鉄砲隊を効果的に使って武田軍を撃破した。
「殿、鉄砲なんぞに頼るのは武士の恥です!」
ある武将がそう言ったが、俺は一蹴した。
「バカ者め。勝つための手段を選んでいる場合か。武士の誇りなど、勝ってから語れ。」

また、安土城を築城し、その壮麗さで人々を驚かせた。
「殿、なぜこれほどの大金を城の建設につぎ込むのです?」
「愚か者め。この城は単なる要塞ではない。我が威光を示す象徴なのだ。」

俺の行動の一つ一つが、古い慣習を打ち破り、新しい時代を切り開いていった。
「信長様、このままでは全国の大名が我らの敵になってしまいます。」
家臣の心配する声に、俺は答えた。
「構わん。敵が多ければ多いほど、勝った時の喜びは大きいのだ。」
そして、俺は着々と天下統一に近づいていった。しかし、運命はまた大きな試練を用意していた。
第四章 – 本能寺の変
天正10年(1582年)6月21日。俺は京都の本能寺に滞在していた。天下統一まであと一歩というところまで来ていた。
前日、俺は家臣たちと宴を開いていた。
「諸君、もうすぐだ。天下統一まであと一歩だ。」
「殿のおかげでございます。」
家臣たちは口々に俺を称えた。その中で、明智光秀だけが黙って酒を飲んでいた。

「光秀、お前どうした?いつもより静かだぞ。」
「いえ、殿。ただ感慨深くて…」
光秀はそう言って微笑んだ。俺は何か違和感を覚えたが、それ以上は何も言わなかった。
その夜、俺は不思議な夢を見た。大きな炎に包まれる自分の姿。そして、背後から刀を振り下ろす影。
「うっ…」
俺は冷や汗をかいて目を覚ました。何かが起こる。そんな予感がしたが、俺はそれを振り払った。
そして運命の日。夜中、突然の叫び声と炎の匂いで目が覚めた。
「敵襲だ!殿、お逃げください!」
家臣の必死の声。俺は状況を把握するのに時間はかからなかった。裏切り者がいたのだ。そして、その首謀者が誰なのかもすぐに分かった。
「明智光秀か…」
俺は苦笑いを浮かべた。光秀は俺が最も信頼していた家臣の一人だった。まさか彼が…
「殿!こちらです!」
忠実な家臣の森蘭丸が、俺を逃がそうとした。
「蘭丸、よく聞け。もし俺が死んだら、秀吉に伝えてくれ。『天下を任せる』とな。」
「何を言うのです!殿は必ず…」
その時、天井が崩れ落ち、俺と蘭丸は離ればなれになった。
本能寺は炎に包まれ、敵兵が押し寄せてくる。逃げ道はない。だが、俺は最後まで諦めなかった。

「来い!この織田信長が相手になってやる!」
刀を構え、迫り来る敵兵と戦う。一人、また一人と敵を倒していく。しかし、数があまりにも違いすぎた。やがて、俺の体は矢で満たされ、刀で斬られ…
最後の瞬間、俺は思った。
「天下統一…あと少しだったのに…」
そして、俺の意識は闇に沈んでいった。

エピローグ
俺の人生は、本能寺の炎と共に幕を閉じた。しかし、俺の夢は消えなかった。豊臣秀吉、そして徳川家康へと受け継がれ、最終的に日本は統一された。
俺が始めた楽市楽座の制度は、日本の商業を大きく発展させた。キリスト教の布教を許可したことで、西洋の文化や技術が日本に流入した。鉄砲の導入は、戦争の形を大きく変えた。
俺の生涯は、野望と挫折、勝利と敗北の連続だった。多くの人々から「第六天魔王」と恐れられ、時に「織田大猿」と笑われもした。だが、それこそが人生というものだろう。
後の世の人々よ。己の信じる道を歩め。たとえその道が険しくとも、諦めるな。古い慣習にとらわれず、常に新しいものを求めよ。そして、常に前を向いて進め。それが、この織田信長からの最後のメッセージだ。
天下統一は果たせなかったが、俺は自分の人生に悔いはない。新しい時代の扉を開いたのだ。これからの日本が、どのように発展していくのか。俺は天国から、きっと見守っているだろう。
(了)